アミラ・ハスへのインタビュー
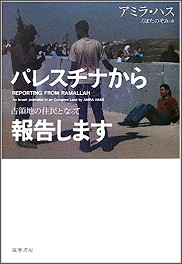
(『パレスチナから報告します』(アミラ・ハス著/筑摩書房)あとがき)
ある新聞記事やルポが書かれた現場にたまたま自分自身も実際足を踏み入れ取材したことがある場合、その記者の取材力や筆力がよく見えていくものだ。ましてや同じ現場に、しかも同時期に居合わせたときはなおさらだ。本書の圧巻ともいえるイスラエル軍侵攻直後のジェニン難民キャンプを描いた28章がまさにそうだった。2002年4月2日に始まった侵攻は11日までおよそ10日間続いた。しかし制圧したイスラエル軍が外から医療関係者らに難民キャンプに入ることを許可したのはそれから4日後の4月15日だった。周囲を包囲したイスラエル軍の監視の目をかいくぐってジャーナリストたちが難民キャンプの中に入り始めたのもこの日からだった。私がキャンプ内で入ったのはその翌日の16日で、アミラ・ハスもほぼ同じ頃、現場に入っている。つまり、まだ死臭が漂い、遺体の一部が瓦礫の間に散乱するあの凄まじい破壊跡を同時に目撃していたのだ。数日後、エルサレムに戻った私はイスラエルの有力紙『ハアレツ』(英字版)のほぼ1ページを埋めたアミラの「ジェニン報告」を読んだ。私は打ちのめされた。読者を現場に引き入れてしまうような詳細な風景描写、猛攻撃にさらされる当時のキャンプ内の様子を住民の目で実際目撃しているかのような錯覚さえ起こさせる証言の数々。3日間に渡って取材したというその記事の深さは、当時、私が読んだジェニンに関する多くの記事の中でも突出し、異彩を放っていた。
私がアミラ・ハスに出会ったのは、1993年10月、「オスロ合意」から1ヵ月後、ガザ地区だった。当時、私は「オスロ合意」がパレスチナ人にとってほんとうの和平につながっていくのかどうかを見極めるために、ガザ地区で最も占領の抵抗の激しいジャバリア難民キャンプのある民家に住み込みを始めていた。その家の長男をコーディネーター兼通訳として雇っていたのが『ハアレツ』占領地特派員となったばかりのアミラだった。「オスロ合意」は調印されても、ガザ地区は当時まだイスラエル軍の占領下にあった。和平ムードが広がり幾分下火にはなってはいたが、それでもジャバリア難民キャンプのような抵抗の拠点では、イスラエル軍と投石する青年たちとの衝突は続き、住民たちが外出禁止令で家に何日も閉じ込められることは珍しくなかった。そんな緊張状態が続くなか、占領地特派員となったアミラは、ガザ市内に一軒家を借りて住み始めた。イスラエル人女性が独り、パレスチナ人社会の真っ只中に住み込む──無謀にも見えるが、アミラにすれば、それは 住民にとって“占領”とは何かを自らの体験を通して知っていくためには不可欠なことだった。アミラがアラビア語を学び始めたのもこの頃である。当時撮影した私のビデオの中に、ガザ市内の自宅でアラビア語の個人レッスンを受けるアミラの映像が残っている。十数年経った今、アラビア語でパレスチナ人と激しい政治議論をしている現在のアミラを見ると、隔世の感があるが。
世界のパレスチナ・イスラエル報道は、えてして「パレスチナ人の蜂起とテロとイスラエルによる報復の連鎖」、つまり「双方の暴力の応酬」として描かれ、説明されがちだ。しかし、この問題の核心は、「暴力の応酬」ではなく、パレスチナ人の暴力を引き起こす根源となっているイスラエルの“占領”である。ただこれは社会、政治、経済のすべてにおよび、住民の日常の生活の中で起こっている“構造的な暴力”であり、視覚でとらえにくい部分も少なくないため、その表現は容易ではない。アミラ・ハスはまさにそれを現地ルポでやってのけた。1996年に英語版でも出版された『Drinking the Sea at Gaza(ガザの海水を飲みながら)』である。1948年にパレスチナの故郷を追われた難民たちとその子どもたちの故郷との深い心の紐帯、今も残る同郷人たちの強い絆、イスラエル刑務所に投獄された政治犯たちの獄中生活、拷問と記憶に刻まれたトラウマ、封鎖政策によって仕事を失っていく労働者たちの苦悩、イスラエル当局による恣意的な通行許可発行の実態、封鎖による経済、産業、医療などへの打撃、自治政府幹部たちの独占企業、腐敗、賄賂の強制、アラファトの独裁、報道の自由の制限・・・・、描かれているテーマはパレスチナ社会のあらゆる分野におよんでいる。しかも住民たちの具体的実例をとりあげ、人々の心の奥の声を引き出しながら、それぞれの生活の実情、社会の現状、その歴史を丹念になぞっていく。これまで“パレスチナ人”という総体で語られてきた人々が、固有名詞をもち、それぞれの個性をもった人物として、等身大で生き生きと文章の中から蘇ってくるのである。読者はその記述を通して、“占領”を単なる抽象的な概念としてではなく、その個々の人々の生活を支配し生死さえ左右する具体的な“力”として感知し、体得していく。
この仕事こそ、まさに私自身がこの20年近いパレスチナ取材で目指してきたことだった。しかも「オスロ合意」直後の1993年のガザ地区やヨルダン川西岸での取材は、時期、地域ともアミラの取材と重なっている部分が少なくない。しかし出てきた結果には雲泥の差がある。悔しいが、それは明らかにジャーナリストとして資質の差だ。一イスラエル人として“占領する側”の政治、社会、経済、文化、そして国民心理まで知り尽くし、歴史研究者としての鋭い洞察力をもち、さらにその仕事が自己の存在意義にまで関わるほどの強い動機をもった記者が、類まれな取材力、表現力をもってイスラエルの“占領”を描くとき、他のジャーナリストの追随を許さないのは当然である。
「説得力に満ちた論点をもつ素晴らしい著書である。ハスは、洞察力に富んだ目と耳でパレスチナ人の逆境の生活の本質と、辛く単調な日常を捉えるいう、途方もなく偉大な仕事やり遂げている」(『ワシントンポスト・ブックワールド』)、「牢獄のような悲惨で危険なガザの生活を、ハス女史のような激しさと精密さをもって表現した記者は他にはいない。彼女はその現実を絶望に似た感情を抱きながら観察し、巧妙に情熱を込めて描き出している」(『エコノミスト』)と世界の各誌も絶賛した。
本書はその続編となるアミラの現地ルポである。舞台はガザ地区からヨルダン川西岸に移っている。『ハアレツ』紙に掲載された記事を集めたもので、前書のように“占領”の構造が体系的に描かき出されているわけではないが、その個々の記事が等身大の住民の生活や声を通して十分に“占領”の実態を伝えている。例えば、31章では、イスラエル軍による封鎖によって、脚の切断手術を受けた母親を、7キロしか離れていない街の病院へ運ぶことの途方もない困難さ、また封鎖によって食料や医薬品を供給できなくなった村人たちの想像を絶する生活困窮の実例を具体的に描き出すことで“占領”とは何かを読者に肌で実感させる。
アミラの記事の特徴は、現場で生きる人々のつぶやきの中から心の襞(ひだ)を紡ぎ出し、読者が現場で当事者たちと同じ視線で、その生活を追体験させられているようなリアリティーを伝えていく表現力にある。住民の生活の中に深く入り込み、長い期間と深い人間関係を作り上げる地道な作業によって、相手に心を開かせなければ決して引き出すことの言葉を丁寧に拾い集め、パレスチナ人の置かれている現実を読む者の前に突き出するのである。例えば、パレスチナ治安警察に拘禁されたイスラム系組織の父親をもつ子どもたちの心の内を描いた5章では、イスラエルではなくパレスチナ当局に逮捕されたことへの周囲の冷ややかな反応、それによって傷つく家族たち、引き裂かれた父への子どもたちの深い思慕と心の屈折、そしてその現実から透けて見えてくるパレスチナ当局の腐敗と矛盾を子どもや母親の言葉によってあぶり出していく。また13章では、ユダヤ人入植者たちや、それを守るイスラエル兵たちの日常的な暴行と恐喝に脅えながらヘブロン市街で暮らす住民たちの声を丹念に再生することによって、私たちをそのおぞましい現場に否が応でも引き連れていく。
一方、アミラは本書の中で、多くのジャーナリストや「パレスチナ問題専門家」たちが見誤ってきた「オスロ合意」以後のパレスチナ情勢を、現場から観察し続けることによって正確に把握し、その将来を見事なまでに予見している。その象徴的な例が7章だ。少なからぬジャーナリストや研究者たちが「現実的な和平の道」と主張し続けてきた「オスロ合意とその後の和平プロセス」は、実は「戦争や混乱に終止符を打つとは思えない」もので、むしろ「アパルトヘイトのような形態に行き着く」ものであるとパレスチナ人の有識者たちが指摘し警告していたことを、アミラは第2次インティファーダが始まる半年も前に報道していた。いや、本書の中でアミラが描いたオスロ合意以後の“占領”の実態そのものが、まさにその立証だったといえるかも知れない。さらに14章では、2000年7月のキャンプ・デービッド交渉に関する「イスラエルのバラク首相(当時)の“前例のない寛大な提案”にパレスチナ側はインティファーダをという暴力で応えた」という通説が実は実態とは大きく食い違うものであったことを伝えている。メディアでその交渉の内実がまだほとんど報じられていなかった交渉決裂からほんの4ヵ月後の11月に、である。アミラはその中で、「あくまで1967年6月4日の国境線に立ち返ることを原則とする」パレスチナ側に対して、イスラエルの提案は「パレスチナ国家が西岸地区が3つの飛び地に分割され、その間の行き来は常時、イスラエル側に握られる」ことになるというのが実態だったことを明らかにしている。
なぜアミラにそれができたのか。現地のテレビや新聞報道、論文などを頼りに情報を集めることが中心で、現場で生きる人々のつぶやきも吐息に耳を傾ける機会もほとんど持たないジャーナリストや「専門家」たちと違い、アミラは徹底的に“現場”にこだわる。ほんとうの“平和”かどうかの指標を為政者たちの言動に置くのではなく、アミラは現場の民衆の声と生活に定め、そこからほとんどぶれることがない。“占領”された人々に笑顔が戻らない限り、ほんとうの“平和”はないというアミラの確固たる信念が、彼女に時代を見通す力を与えているように思える。
本書は2002年10月で終わっている。その後のパレスチナ情勢をアミラはどう見ているのか。
2003年4月には欧米諸国の圧力によってアラファトは、マフムード・アッバスを初代首相に任命し、権力の一部を移譲することを受け入れた。アッバス首相はブッシュ大統領が提唱した和平案「ロードマップ(工程表)」を推進するためにイスラエル側と話し合いを進めた。しかしアミラはこの和平案に悲観的だった。「ロードマップの基本にあるのは実質的な“占領”です。その中心になっているのはパレスチナ人のテロ対策です。まったく論理が逆転しています。イスラエルはパレスチナ人の民族的な権利を認めるつもりはまったくない。今のブッシュ政権はこの状況を突破し解決するためにイスラエルに圧力をかけるつもりはないのです」。2003年4月、アミラはラマラで私にそう語った。果たしてその後、ユダヤ人入植地や分離壁の建設を推し進めるイスラエルとの交渉はなかなか進展しなかった。一方、アッバス首相がハマスなどイスラム武装勢力と結んだ停戦協定も、イスラエルがハマス活動家らの暗殺作戦を停止しなかったためにハマスが反発し自爆攻撃を再開、それに対しイスラエルはハマス幹部の暗殺で報復し、停戦協定は完全に破綻してしまった。またアッバス首相は権力の移譲を拒むアラファトとの確執によって辞任に追い込まれ、イスラエルとの交渉は頓挫した。
次の大きな転機は、2004年11月、アラファトの突然の病死によって訪れた。その2ヵ月後に行われた議長選挙によってパレスチナの新しい指導者となったアッバスは、パレスチナ内の武装勢力に武装闘争の停止を呼び掛けた。また2月にはシャロン首相との首脳会談で、お互いの武力による攻撃を停止する「停戦宣言」を発表した。その1年前に、シャロン首相が発表した、ガザ地区からすべてのユダヤ人入植地を撤退するという「ガザ地区撤退計画」と共に、和平ムードがいっきに高まった。しかしアミラは冷めていた。ガザ撤退計画についても、「シャロンには明確な意図があります。ヨルダン川西岸の植民地化をいっそう進め、その土地をできるだけ多くイスラエルに併合することです。ガザ地区から入植地を撤退することでイスラエル和平派の反発を抑え、世界に全占領地からの撤退が進行しているような希望を与える。シャロンの目的は、パレスチナ人のコニュニティーを切り裂くことです。つまりパレスチナという一体化した領土をばらばらにすることなのです」と言い切った。またパレスチナの新指導者アッバスへの期待についても、こう評する。
「アッバスたちは大きな罠に落ちようとしています。それは“領土の解放”の重大さを認識できていないことです。『オスロ合意』について民衆を誤った方向へ導いたときと同様、アッバスとその周辺は『パレスチナ国家の建設』について語ってはいます。しかし領土が解放されない限り、国家の建設などありえません。現在、イスラエルはパレスチナ社会のすべてをコントロールしている。もしこの状況を変えようとするなら、占領された人々や土地を解放するためにイスラエルに挑戦しなければならない。しかし“オスロ合意的な発想”の問題は、指導者があたかも“領土と住民を解放する”ようなふりはするが、実際はそうではないことです。だからアッバス政権への期待はゼロなのです」
アミラ・ハスへのインタビュー
何がアミラをジャーナリストとしてそこまで駆り立てているのか。イスラエル人が“パレスチナ問題”を伝えることの意味は何か。ホロコースト体験者の両親をもつユダヤ人であることが、占領地取材にどう影響を与えているのか。そしてジャーナリストとはどうあるべきなのか。2003年4月(ラマラ市)と2005年1月(ガザ市)の2回にわたってアミラにインタビューした。
(Q・イスラエル人がガザ地区やヨルダン川西岸に住み着くことは危険だったはずなのに、どうして敢えてそうする決意をしたのですか)
「それはジャーナリストとして当然の選択でした。パレスチナ人社会について取材しようとすれば、その社会の中で暮らす必要があります。もし日本の特派員に任命されたら、中国ではなく日本に住むはずです。それは当然のことです。
オスロ合意(1993年9月)直後、『ハアレツ』は私にガザ地区の特派員になるように提案してきました。しかし会社は私がそこに住むことまでは予想していませんでした。しかし私はそこに住み込みたかった。“占領”を自分で体験したかったのです。私たちが一般に見ることのできない“イスラエル”の顔を見ることが重要でした。特派員となることは、私にとってそのためにいい機会でした。
1991年から私はガザ地区の住民といい関係を持っていました。「労働者ホットライン」というNGOのボランティアで、パレスチナ人労働者に給料の支払いをしないイスラエル人の雇用者に対し、労働者の代理人として支払いを求める仕事をしていました。つまりガザ地区の住民との接触は人権問題から始まっていたのです。住民が私のかつてのその活動を知っていたこと、私が左派であり、占領に反対していることを知っていたことが、住民のなかにに入っていくのにとても役に立ちました。私は自分の意見を持たない“中立者”としてガザ地区に入っていったのではないのです。
『特派員』になると私はすぐにガザ地区に住み始めました。彼らは私にとって決して目新しい人々ではなく、住民たちもまた私をすんなり受け入れてくれました。ガザ地区の社会はとても外から人間にオープンな社会です。私は自分がイスラエル人であることをけっして隠したりしませんでした。
人々は私とヘブライ語で話をすることを躊躇しませんでした。『ヘブライ語をしゃべるとイスラエルのスパイと疑われる』という心配をしないのです。それは「彼女は大丈夫だ。疑う必要はない」という“メッセージ”でもあったのです。
パレスチナ人社会に住み着くための“鍵”は、普通に行動すること、そして人々に敬意を払うことです。そしてその社会で尊敬されている人々と接触を持つことです」
(Q・あなたの記事のなかで私がもっとも衝撃を受けた記事の一つが、2002年4月、イスラエル軍のジェニン難民キャンプ侵攻直後に書かれたルポでした。私もあなたと同じ時期にあの現場を取材していました。あの当時、何百という家を破壊され、100人近い住民が殺害された直後のジェニンの住民たちはイスラエル軍に対してだけではなく、イスラエル人全体に対して激しい憎悪と復讐心に燃えていました。同じジャーナリストであっても、イスラエル人であるあなたは私たち外国人とは比較にならないほど危険な状況だったはずです。そんな中で、あなたはどうして現地に飛び込んで取材する勇気がもてたのですか)
「それは『勇気』の問題ではありません。私は長くパレスチナ社会で暮らして、パレスチナ人はどういう人たちであるかを知っていました。いつ彼らを信頼できるのか、いつ危険なのか、どんな人とすぐに話しができるか、をです。相手のことをよく知っていれば、恐怖心を持つことはありません。非常に特殊なケースを除いて、私は自分がユダヤ人であり、イスラエル人あることを隠すことはありません。この4年間で2,3回だけそういう例外がありましたが。
私がジェニンに入ったとき、ほんの5分も経たないうちに、人々が私に話しかけてきました。イスラエル軍はまだ周囲にいました。私はすぐに自分がイスラエル人であることを告げました。住民はまだトラウマに苦しんでいる時期でしたが、それでも住民はすぐに私を受け入れました。もちろん全員が喜んで受け入れたわけではありませんが、少なくともだれも私を殺そうとは思いませんでした。パレスチナ人は寛大な人々です」
(Q・ジャーナリストとして活動のなかで、どういうことに主眼を置いていますか)
「私はジャーナリストとして「ビックネーム」(有名人)を信用していませんから、情報を得るために有名人のところへは行きません。当局の役人たちは私にとって「嘘の技術者」です。NGO関係者と話をすることもやめました。彼らもレコードのように同じことを語るからです。
私は、真実を語る人々と話をすること以上に重要なことはないと思っています。私にとって一般民衆が第一のニュース源です。状況についてはまず民衆から学ばなければなりません。それは自明のことです。歴史を専攻した私にとって、取材は毎日の研究のようなものです。それを民衆からやるのです。
例えば野菜を売っている露天商の人から、私は人々の心情、経済状態、交通や封鎖の状況、パレスチナ人の歴史などたくさんのことを学びます。だから一般民衆を取材し学ぶことは私にとって自明のことなのです。一方、取材対象としていつも同じ人間を選んでいるわけではありません。私は検問所、学校、商店、家庭などに出かけていきます。もちろんすべてのジャーナリストがそうすべきだと言っているのではありませんが」
(Q・“占領される側”のパレスチナ人でもない、第三者の外国人でもない、当事者でしかも“占領する側”のイスラエル人のジャーナリストが、パレスチナ問題を伝えることには、どういう特殊性があり、特別な意味があると思いますのか)
「私はそれほど“パレスチナ問題”について記事を書いているつもりはありません。まさに“イスラエルの問題”を書いているのです。それが、私が“占領”について報道する最大の動機です。もちろん、占領下のパレスチナ人の状況について書きます。しかし私は“パレスチナ問題の専門家”というより、はるかに“イスラエルの占領の専門家”なのです。私は“イスラエル占領の進展”の専門家です。だからまさに“イスラエルの問題”なのです。パレスチナ人は生活のすべての面でイスラエルのコントロール下にあります。占領の操作、植民地政策など占領下のパレスチナ人に関するいかなる事柄も、直接、“イスラエルの問題”なのです。他のイスラエル人記者がイスラエルの地方政府や中央政府について書くように、私は“イスラエルのもう一つの局面”を書いているのです。
外国人ジャーナリストがイスラエルの占領について書くとき、まず『偏向していない』ことを証明しなければなりません。たとえば『自分は反ユダヤ主義者ではない』といった具合にです。しかし私は『反ユダヤ主義者ではない』ということを証明する必要などありません。私がユダヤ人自身だからです。“イスラエル人”である以上に、私は自分を“ユダヤ人”だと考えています。だから『反ユダヤ主義者』ではないのです。
しかし多くの外国人ジャーナリストは『どちらにも偏らない』ことを約束させられる。私は『ジャーナリストが偏らない』という考え方には反対です。南アフリカのアパルトヘイトについて記事を書くとすれば、私は一方の側に立って書きます。もし私がレイプについて記事を書くとすれば、もちろん私は決して『客観的』『偏らない』ではありえません。それなのに、どうして“占領”に対して『客観的』『自分の意見を持たない』ことができましょうか。だからイスラエル人である私にとって、“占領”について書くことは(外国人ジャーナリストより)やさしいことなのです」
(Q・報道は「客観的でなければならない」と強調され、「一方の側に立って書くことはあってはならない」とよくいわれますが)
「それはまったくナンセンスです。もちろん伝える情報は“公平”であるべきです。いろいろな情報をチェックする必要はあります。しかし自分の意見は持つべきです。私たちは牛やロバではないのです。私は『客観的』といういことがほんとうのジャーナリズムの原則とは思いません。すべてのジャーナリストは報道するとき、それぞれの意見を持っているものです。もし自分の意見を持たないとしたら、それはいったいどういうことか。そのこと自体が大きな問題です。だれも『客観的』などではありえないのです。重要なことは読者がその意見を知ることです。私は占領に反対です。それを隠して記事を書く意志はありません」
(Q・占領下で過酷な生活を強いられるパレスチナ人の状況を伝えるあなたの記事をイスラエル国内ではどのように受け止められているのでしょうか)
「それは私にもよくわかりません。ただ私がイスラエル軍の作戦における兵士たちの行動について書いたとき、軍の複数の将校が私の記事は正確だと評価しました。もちろん私の情報は軍からではありません。一般の住民から得た情報です。つまり住民たちが正確な情報を私に与えてくれたのです。私はいつもその情報が正しいのかどうかを判断するかはすでに学んでいます。また全体像を得るために十分な数の人々から情報を得ます。
この2,3ヵ月、イスラエル当局がヨルダン川西岸で“バンツスタン”を作ろうとする政策の調査に没頭してきました。その一例がイスラエルがユダヤ人専用道路の建設計画です。イスラエルはその建設費用をパレスチナの援助国に払わせようとしていたのです。その道路はパレスチナ人の道路に代わるユダヤ人専用の道路で、“アパルトヘイト道路”に変わってしまう道路です。最近、私はその記事を『ハアレツ』紙に掲載しました。それによって、援助国が一斉にその件でイスラエルに反対する立場を明確にしました。アパルトヘイト道路になってしまう道路建設を資金援助すれば、その道路はパレスチナ人にとって決して望ましいものではなく排除されるべきだと、私の記事によって援助国はその道路建設にいっそう強固に反対するようになったのです。ただ私の記事の力によってだけではなく、『ハアレツ』がそれを一面で報じ、その重要性を強調したことにも寄ります。
もう一つの例として、『シャバック(国内治安情報機関)』の元長官アミ・アヤロンは、『パレスチナ人の状況はアミラの記事から学んだ』と語りました。『シャバック』の現役長官だった時のことです。私にとってとても重要だったのは、オスロ合意から数年後、アヤロン氏が、パレスチナ人にはこの合意が『平和への道』ではないとみなされ、その不満が(蜂起として)爆発する時期が迫っているということを私の記事から知ったということです。
一般のイスラエル人について言えば、私に限らず、パレスチナ社会をよく知り、イスラエルで一般に広がっている『パレスチナ人観』(例えば『パレスチナ人はテロリスト』といったイメージ)を受け入れないような者たちは“裏切り者”と見られます。私たちは『やつらはパレスチナ人のことばかり心配している連中だ』と見られ、イスラエル社会のアウトサイダーだとみなされるのです。しかし私を『裏切り者』と呼ぶ人たちがどんな人たちかが問題です。もしファシストたちが私を『裏切り者』だと呼ぶとすれば、それは私にとって誇りに思うことです」
(Q・一方、多くのパレスチナ人からあなたの記事は高く評価されています。それはあなたの励みになりますか)
「いいえ。私が事実を目撃し、何が起きているかを知り、それを記事にしているのに、イスラエル人の大半がそれを読みたがらず、私の言うことを聞こうとはしない現実は、私にとって決して簡単なことではありません。当事者であるイスラエル人以外の世界の人々が私の声を聞いてくれても、私には大きな助けにはなりません。またそれは状況を変えることにはつながりません」
(Q・海外のメディアのイスラエル・パレスチナに関する報道、テレビや新聞などを見て、どういう印象を持っていますか)
「私はあまり海外のメディアを追ってはいません。そんな時間がないのです。ただテレビは一般的に内容が浅いので、むしろ内容がテレビよりも深い活字メディアはときどき目にすることはあります。『ガーディアン』とか『インディペンデント』とか『ルモンド』とかです。中にはとてもいい記事があります。それらの記事を書いている記者は、たいがい現地に3、4年滞在しているジャーナリストたちです。とても勇敢に現場へ入っています。私はテレビよりそれら活字媒体から多くのことを学んでいます。テレビ報道が浅薄であることは、ここだけではなく、全世界で共通の問題です」
(Q・あなたは以前私に、自分のジャーナリスト活動の原動力は「怒り」だと言いましたね)
「『怒り』が私の“ガソリン”です。ときどき人々が、どうしてそんなにエネルギーがあるのかと訊くんです。“怒り”です。“怒り”が私にエネルギーを与えているのです。朝、起きると、パレスチナ人の誰かが検問所から電話してきて、通過できず職場にいけないと訴える。2時間後には、また他の人が分離フェンスのゲートがあかず、オリーブの収穫に行けないという。3時間後には、ガザ出身でラマラに住んでいる友人がイスラエル兵に拘束されたと聞かされる。だからいつもこのような“不正義”のために怒りを抱いてしまう。私は自分の住んでいるラマラから、イスラエル人ジャーナリストである特権のために自由に行き来できる。自分だけそれができることにまた怒りがこみあげてくる。入植地に行くと、それはまさに植民地主義の象徴であることを目の当たりにして、また怒る。ラマラからテルアビブに行くと、イスラエル人市民が通常の生活をしている。それを見て、また怒る。だからいつも私は怒っているんです。
その一方、私は人々との関係のなかで、自分が“豊か”になったと感じています。とりわけ難民キャンプや村においてです。私のようなイスラエル人がジェニンやラファ、ベツレヘムで、イスラエル軍の外出禁止令の下、銃撃の中でパレスチナ人の家族の世話を受けることがあります。家のなかで、家族とヘブライ語で会話している。そんな体験が私をとても“豊か”にしています。内面が“豊か”になっているということです」
(Q・“豊か”になるということはどういうことですか)
「私はこの5、60年のパレスチナ人の苦難を顧みるとき、狭苦しく、水道も電気もない難民キャンプのようなひどい環境の中で暮らしながら、どうして人間としてあれほど美しくあれるのか、つまりあれほど他人に寛大で、優しく、ユーモアのセンスがあり自分を笑い飛ばすことができるのかと自分に問いかけるときがあります。これほど緊迫し困難な状況のなかでも、このようなヒューマニティ(人間性)、寛大性さ、人間としての尊厳を人々が保っている。それが私を“豊か”にするのです。
もちろんパレスチナ社会には欠陥もたくさんあります。私はときどきパレスチナ人のことを『馬鹿だ』『無知だ』と言い放つことさえあります。アラファトは私を2度、パレスチナから追放しようとしました。1度はガザ地区で、2度目はこのラマラからです。その都度、パレスチナ人の誰かが間に入り、アラファトにその要求を却下させたのです。それはたいへんな勇気がいることです」
(Q・あなたがパレスチナにおける占領について書くとき、ご両親がホロコーストの生存者であることに何か関わりがありますか)
「私はそれを否定するつもりはありません。ただ私は世界を国家や民族によって分けることはしません。私の原点、忠誠心を持つ対象は親族や家族ではありません。それよりも、もっと関係があるのは、私が“左派の思想”を持つ家族の中で育ったことです。つまり民族的なビジョンは重要ではないという考えを持った家族の環境の中で育ち、物心ついたころから、占領や差別に反対してきました。そしてジャーナリストという職業が、よりいっそう強くその“自分の原則”に沿って生きることを可能にしてくれました。
私たちの家族がホロコーストの生存者であることの教訓と結論は、『“抑圧”に反対する』ということです。だから世界のいかなる問題にも私は“抑圧される側”に立ちます。世界第二次大戦のときなら、私は日本に反対する立場に立っていたでしょう。アパルトヘイトの南アフリカでは私は黒人の側に立っていたでしょう。自分が白人だからと言って、自動的に当時の白人政権の側に立つということではないのです。だから私を動機づけているのは、家族の“伝統”です。
また一方で、自分が“ユダヤ人”であることも、重要な要素です。それは“平等”が私たちの社会生活、人間としての生活の基礎であるということを理解しているということです。だからイスラエルの行動の“不平等”に対する疑問と怒りが、私のジャーナリスト活動を大きく動機づけているのです」
(Q・あなたのお母さんたちユダヤ人が強制収容所に連行されるのをドイツ人たちが傍観していたというお母さんの体験が、あなたを「客観的な立場」「第三者の立場」に立つことを拒否させているのですか)
「いいえ。私が言っているのは『傍観者』にはならないということです。『傍観者』であるということは、『無関心』だということです。つまり不正義に対し無力感を持ち、何もしないということです。私の母は多くのユダヤ人と同様にドイツ国内の強制収容所に送られました。彼女はそのとき死にたいと思ったと私に語ってくれました。彼女は家畜貨車で運ばれました。10日間、ほとんど食べることも水を飲むこともできませんでした。動物のような状況におかれました。その後、貨車から降ろされ、強制収容所まで歩かなければなりませんでした。その沿道にドイツ人の女性や男性たちがそれを見つめていました。いわゆる『無関心の好奇心』の目でした。その頃の母の写真を見たことがあります。私がそこにいるような錯覚に陥りました。もちろん、実際はその現場にいたわけではありません。それは私にとっていつも憎むべき『傍観者』の一例でした。まったく気にかけないか、または自分がまったく無力感の状態にあるかです。
ただ私がこんな考えを持つのは、ただ私がただ単に『ユダヤ人』であるからではありません。自分が『左派』だからです。(両親は)当時、共産主義や社会主義の考え方を持っていました。『介入しない。傍観者にはならない。不正義がまかり通らないように行動する』、つまり“ヒューマン”であることです」
(Q・あなたが占領について伝えようとするとき、イスラエル人のジャーナリストとして、“ミッション(使命感)”のようなものを感じますか。ジャーナリストはどうあるべきだと思いますか)
「私自身、仕事を通してジャーナリズムにあり方についての考えを発展させています。ずっと一貫しているとは思いません。ただジャーナリストの主要な仕事は“権力中枢をモニター(監視)すること”です。つまり支配者がどのように被支配者に影響を及ぼしているかを観察し、批判することです。ジャーナリストは弱者を追跡するスパイとなるべきではありません。強者をこそ追跡するべきです。
私たちの国イスラエルはパレスチナ人にとってまさに“権力の中枢”です。だから私がやっているのは、イスラエル国民に“権力の中枢”である私たちがパレスチナ人に対して何をしているかを描き出し、それを彼らの目の前に突きつける、ということです」
(Q・日本人はこのイスラエル・パレスチナ問題を「地理的にも心理的にも遠く、複雑で難しい問題」と考え、敬遠しがちです。この問題は日本人とどういう関連があると思いますか)
「日本は、パレスチナ社会に対する大きな援助国です。だから日本の納税者たちはその税金がどこへ行っているのか知る必要があります。去年、取材でわかったことは、パレスチナ当局に対するあらゆる援助国の金は、結果的にイスラエルの占領を“補助”しています。たとえばイスラエルがパレスチナの道路や建物を破壊し、それを修復するために援助国の資金が使われます。またイスラエルの“封鎖政策”のためにパレスチナ人が貧困に追いやられ、貧困に瀕したパレスチナ人たちを救援するために支援国の援助が使われていきます。つまり日本など海外からの援助がパレスチナ社会の発展のためには使われず、イスラエルの“占領”が引き起こしている損害の“弁償”に使われているのです。だからこそ日本の人たちはこの問題に無関心であってはいけないのです。
(Q・あなたはこの翻訳された著書で、読者にどんなメッセージを伝えたいですか)
「日本の人口は1億2千万人なのに対し、現地のイスラエル人とパレスチナ人合わせても800万人から900万人です。日本のような大きな国が、パレスチナ・イスラエルのような、日本の1都市ほどの小さな地域に関心を持つことに不思議な気がすることでしょう。しかしイスラエル・パレスチナ紛争は、国際問題の中核ですから、自国の政府がこの地域と問題に対してどういう政策をとっているのかを知る必要があります。
ただ罠にひっかかってはいけません。オスロ合意のときには、『交渉』自体が『平和』を意味していました。日本人だけでなく、多くの国の人がそう信じこんでいました。日本は今後もこの地域への援助を通して、いろいろな形で将来の和平交渉に関わることになるでしょう。だからこの地域にパレスチナ人が400万人しかいないということは重要な問題ではありません。
世界のあらゆる人たちが注意し、また行動を起こすべきことは、新たなシステムの“アパルトヘイト”が今、この地域で広がっていくことを阻止することです。それはパレスチナ人自身、またそれに関わる中東地域にとってのみ危険なのではありません。ユダヤ人にとっても危険だからです。私はユダヤ人ですから、当然、同胞たちのことを気にかけます。その同胞たちが『軍事的な優位だけが自分たちの将来を保障することができる』と信じ続けるとしたら、ユダヤ人社会の将来にとってとても危険なことなのです」
2005年2月記

