日々の雑感 231:
山形国際ドキュメンタリー映画祭/報告(2)
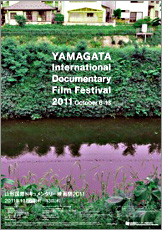
2011年10月9日(日)
- 『日は成した』
- 『ちづる』
- 『阿仆大(アプダ)』
- 『失われた町のかたち』
- 『大津波のあとに』
『日は成した』
スイス/2011/111分
監督:トーマス・イムバッハ
自分の部屋から見える風景の映像に、留守番電話に残されたメッセージの音声を重ねていく。誕生日を祝う家族の言葉、喧嘩した恋人なのか、謝罪する声……。なぜこんな映画が1000本を超える応募作から選ばれ、この映画祭で観せられるのか理解できない。もっと他に観なければならない映画があるはずだと焦り、十数分で劇場を飛び出した。
『ちづる』
日本/2011/79分
監督:赤崎正和
若い作者が大学の卒業作品として、自閉症の妹とその母親を撮った作品。家族だからこそ撮れる家族の“裸”の姿の緊迫感がそのまま作品の力となっている。一方、家族だから外に晒(さら)したくない、隠しておきたい心理も作者には働いたはずだ。「誰のために、何のために作品にし、他人の目にさらすのか」という自問と葛藤の声を、作品の中でこの若い作者からもっと聞きたかったし、その姿を観たかった。
『阿仆大(アプダ)』
中国/2010/145分
監督:和淵(ホー・ユェン)
中国の山奥の村に生きる少数民族ナシ族の農夫アプダと、老いて体の自由のきかない父親の生活を固定したカメラで淡々と描いた作品。映像はしっかりしている。しかし私は何を伝えたいのか、なぜその映像を見せられるのかがわからず、40分ほど我慢したが、耐えられず劇場を出てしまった。
ホー・ユェン監督は自分のドキュメンタリー映画観を公式カタログの中にこう説明している。
映画はイメージと音声の共同作業をもたらす芸術だと考えている。そしてドキュメンタリーとは、芸術の一様式やカテゴリーというより、映画的手法なのだと思う。それは映画制作の数多い創造的な方法のひとつでしかない。写生にも似て、ドキュメンタリー映画の制作とは芸術家と世界との接点を表すものだ。それは、カメラやマイクや三脚といった映画の器材を外界に担ぎ出すことである。ちょうど画家が絵の具やイーゼルを屋外に持ち出し写生するように、ドキュメンタリー映画制作者は、小道なり、村なり、野原なりに入り込み、そこで発見した生に直面し、そして仕事を開始するのである。生命や存在と直接的で親密な関係を結ぼう、という呼びかけに応えたいという気持ちを、このやり方は示している。「自然から学べ」とは古代中国の画家たちが繰り返し言ったことだ。ドキュメンタリー映画制作とは、この教えをシネマトグラフという形式において実践する手法そのものなのだ。
私がこのような映画に惹かれないのは、作者と私の“ドキュメンタリー映画”観の違いからだということに気付く。私はドキュメンタリー映画を「映画はイメージと音声の共同作業をもたらす芸術」とも、単なる「映画的手法」「映画制作の数多い創造的な方法のひとつでしかない」とも、単なる「写生」とも考えていない。私はむしろジャーナリズムの一手法として、伝えなければならない社会的なテーマ、人間の普遍的なテーマを、活字ではなく映像で表現し伝えるのが“ドキュメンタリー”だと考えている。だから伝えたい社会的なテーマ、人間の普遍的なテーマが前半の30分ほどで伝わってこない(おそらく最後まで観れば、わかるような作りなのかもしれないが)「ドキュメンタリー」は辛抱してみることができない。
前回の山形映画祭で私が持った、「なぜこんな映画がこの山形映画祭に選ばれるのか」という疑問と苛立ちは、映画祭の選者たちに主要な問題があるからではなく、“ドキュメンタリー”という概念を狭くとらえ過ぎている私の側の問題にこそ起因するのだということがだんだんわかってきた。しかし私の“ドキュメンタリー”観を変えるつもりはない。ただもう少し、違う“ドキュメンタリー”観を受け入れる度量が私には必要なのだろう。しかし一朝一夕には度量は大きくなりそうにもない。この映画は「素晴らしいドキュメンタリー映画」の1つなのかもしれない。しかし、私にとって2時間25分も見続けられる映画ではなかった。
この映画を高く評価するある人の中には、「他の多くの映画のように忙(せわ)しいテンポではなく、ゆったりとしたテンポで流れていくのがむしろ心良かった」という声もある。なるほど、映画制作の動機がすぐに見えてこないことに苛立ってしまう私の短気さが、「いい映画」を見逃してしまう大きな要因となっているのかもしれない。
『失われた町のかたち』
アメリカ、ポルトガル/2011/92分
監督:ジョン・ジョスト
『アプダ』から逃げるように、『失われた町のかたち』の劇場へ入った。リスボンの街角の「何の変哲もない日常風景」を描いた映画。これにも私は「何を伝えたいのか、なぜその映像を見せられるのか」が理解できず、10分足らずでまた飛び出した。
『大津波のあとに』
日本/2011/73分
監督:森元修一

失望と苛立ちを抱え、逃げるように大震災特集「ともにある Cinema with Us」の会場へ移った。『大津波のあとに』の上映劇場は満席で、後ろは立ち見の客が並んでいた。大震災に関するドキュメンタリーへの関心の高さ、熱気が伝わってくる。若いドキュメンタリスト・森元修一が石巻市を自転車で回りながら、瓦礫と山となった街を撮っていく。とりわけ児童108人中74人が津波にのみ込まれた大川小学校に遺体や遺品の捜索に来た遺族たちを声をかけながらカメラを回していく。痛みを抱える人に控えめにそっと“寄り添う”ようなその声掛けに、撮影者の謙虚で誠実な姿勢、一方で“伝えなければ”という情熱が伝わってきて、好感のもてるいい作品だった。皮肉にも、この大震災は若い優れたドキュメンタリストたちが育つ機会を与えたのかもしれない。多くの犠牲者を生んだベトナム戦争が、優れたカメラマンやジャーナリストを育てたように。
『アプダ』『日は成した』『失われた町のかたち』から次々と逃げ出してきた私は、観たいドキュメンタリー映画にやっとたどりついたという思いだった。それは、自分がどんなドキュメンタリー映画を観たいのかを改めて自覚させられるプロセスでもあった。
(追記)
『アプダ』は「インターナショナル・コンペティション」部門の優秀賞を受賞した。
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。
