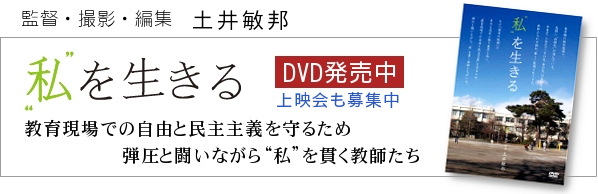日々の雑感 250:
『“私”を生きる』の劇場公開に寄せて(1)
2012年1月19日(日)

1月14日、ドキュメンタリー映画『“私”を生きる』が東京で初めて劇場公開された。初日の観客数は幸い、130席の劇場が満席となった。その日の「朝日新聞」の都内版に写真入りで大きく紹介されたことも効いたようだ(朝日新聞:異議の3教員、映画に 君が代斉唱で東京都教委と対立)。
実はこの映画の制作時には、劇場での公開は計画していなかった。「日の丸・君が代」という微妙な問題に触れたこの映画を、敢えて上映する勇気ある劇場を探すのは難しいだろうと思ったからだ。この種の映画はDVDで地道に広げていくしかないと判断し、最初からDVDを製作し、ネットとメール、さらに上映会、シンポジウムなどを通して広報し販売してきた。支援者の広いネットワークを持つ3人の出演者の方々の影響力もあって、かかった経費を賄えるほどには売れた。
しかしDVDの広報や販売の範囲には限りがある。やはり出演者の関係者や支援者たち、学校の教員など学校教育に直接関わっている人、また教育問題に関心のある人が大半で、それ以上にはなかなか広がってはいかない。「映画は映画館で上映されて一般の観客に観てもらってはじめて“映画”になる」。ある映画製作者にそう言われた。これまで“パレスチナ”をライフワークにしてきた私が初めて国内のテーマを扱ったこのドキュメンタリーが果たして“映画”として通用するのか。私がこの映画広報のコピーに謳った「これは『教育』問題や『日の丸・君が代』問題を論じるドキュメンタリーではない。大きな社会の流れに独り抗い、凛として生きる“生き様”を描いた」狙いが一般の観客に伝わるか。私はそれを映画館での上映で問うてみたいと思った。
しかしそれには大きな壁があった。まず資金だ。映画上映のためには最低でも100万円近い資金が必要となる。収入の少ない私には大金だ。その経費を賄えるほどの観客を呼べなければ、すべて赤字となり、自腹を切らなければならなくなる。また上映のための準備、広報、上映中のトークショーなど映画上映のために多くの時間を割かなければならず、そのために他の仕事を一時中断することも覚悟しなければならない。お金や時間のことだけを考えれば徒労のように思えるが、「自分の仕事を世に問い、伝える」という意味ではやらなければならないと思った。
もう1つの壁は、この作品を「劇場で公開できるだけの質がある」と認めてくれる劇場があるかという問題だ。しかも「日の丸・君が代」という、一部の勢力からの攻撃の対象になりかねない微妙な問題が扱われている。大半の劇場の支配人たちは躊躇するかもしれない。実際、東京のある劇場からは断られ、横浜のある劇場からは無視されてしまった。ただどうしても確認したかったのは、この映画は、劇場での上映に耐えられるほどの質なのかということだった。この映画は企画から取材、撮影、編集まで独りでやった作品である。それがプロの作品として通用するのかどうか、つまりドキュメンタリストとしての自分の資質がプロとして通用するものかどうか、劇場で上映できるドキュメンタリー作品を作れる力が自分にあるのかどうかをどうしても知りたかった。もちろん前作の『沈黙を破る』も粗編までは独りで制作した作品だが、最終段階でプロの編集者やプロデューサーの力も借りた。それにあの作品は私がライフワークとして長年、自分の半生を賭けてやってきた仕事の一部だったから、ある程度、自信もあった。しかし今回はまったくこれまで関わってこなかった国内のテーマを扱ったもので、まさにドキュメンタリストとしての自分の資質が問われる作品だと思った。だから、作品への評価が前作以上に気になった。
この映画がどの程度のものなのか試すために、まず挑戦したのが昨年の「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」だった。幸い、最終選考作品の1つに選ばれ、「奨励賞」をいただいた。次に挑戦したのは「山形国際ドキュメンタリー映画祭」だった。無謀にも、世界中から名作が集まる「コンピテーション部門」に応募したが、予想通り候補作品にはならなかったが、日本人作品から選ぶ「ニュー・ドックス・ジャパン」上映作品の1つに選ばれた。意外な結果に驚いた。「ドキュメンタリー映画として通用する」と言ってもらった気がした。
「渋谷の映画館の支配人が、来年1月だったら上映してもいいと言ってますが、どうしましょうか?」とある映画配給会社の方から連絡を受けたのは昨年10月、私が中東取材の準備をしている時だった。1月中旬までもう2ヵ月ほどしかない。正式に決まったらすぐに準備にかからないと間に合わないが、本決まり前に、この中東取材を中止するわけにもいかない。私は予定通り、10月下旬、エジプトのカイロへ向けて飛んだ。映画上映が正式に決まったのが11月中旬、私がエルサレムに滞在しているときだった。配給・宣伝は「浦安ドキュメンタリーオフィス」の中山和郎さん、「スリーピン」の原田徹さんが引き受けてくれることになり、海外取材中の私に代わり、連れ合いの幸美が自分の仕事の合間を縫って製作側の代表として、中山さんたちや劇場側との協議や準備に奔走した。
私が帰国したのは劇場公開の初日まで1ヵ月ほどしかない12月12日だった。その3日後、マスコミを対象にした試写会が開かれた。通常数回行われる試写会も資金不足で1回だけ、出席したマスコミ関係者の数も10人にも満たなかった。いったい劇場に観客は来てくれるのだろうかと不安だった。私はメールやツイッターで必死に友人、知人に映画の広報とチケット販売の協力を呼び掛けた。幸い、多くの方が私の要請に応えてチケットの買い取りや販売で協力を申し出てくれ、650枚の「上映協力券」をさばいた。予告篇は、横浜国大の学生時代に私のボランティアとして手伝ってくれ、今は自ら映像制作会社を立ち上げ「社長」になった森内康博さんが担当し、A4サイズで3つ折の簡単なパンフレットは急きょ、私自身が編集した。
1ヵ月あまりのあわただしい準備の末に迎えた初日、映画館ロビーが上映を待つ観客で埋まったとき、驚き、ほっと安堵し、胸が熱くなった。上映期間の1週間延期が決まった。
【追記】
1月20日、映画上映後のトークショーに登場していただく元NHKプロデューサーで武蔵大学教授の永田浩三さんが初日の感想を書いてくださった。
土井敏邦監督の「私を生きる」を見た
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。