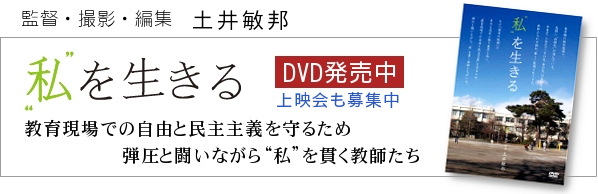映画『”私”を生きる』トークショー
ゲスト:永井愛さん(後半)
→映画『”私”を生きる』トークショー ゲスト:永井愛さん(前半)
2012年1月17日 東京:オーディトリウム渋谷
ゲスト:永井愛さん(劇作家/演出家/劇団「二兎社」主宰)
土井:私はやはりこの言葉が非常に残っています。実は、2010年11月のシンポジウムの中で、永井さんが、「心のありか、『節』」いう言葉を語っていらっしゃったんです。日本人にない、つまり良心の拠りどころが日本人はどこにあるのかという問いかけをされましたが、永井さんの口から、このことについてもう少し説明いただけますか?

『かたりの椅子』の戯曲は
『せりふの時代』2010年5月号
に掲載されています
永井:翻訳家の松岡和子さんが、「integrity」という言葉が出てくると、ぴったりくる日本語がなくて訳すのに困るとおっしゃたんです。私の書いたこの戯曲が、基本的に「integrity」の問題だということで、その話になったんですけれども。「integrity」は、よく「正直」「高潔」「誠実」などと訳されるそうですが、松岡さんの感じでは、どれもみんな、他人の目が入っていると言うんです。対社会的に見て、社会的に判断してそうであると言えるというような、つまり他者からの評価が入っているということです。でも、「integrity」とは、社会的な目を排して、もっと自分自身に問いかけるような、自分と交わした契約のようなものだそうです。だから、「これでいいのか」と自分に問い返した時に、「これでいいんだ」と言えるような状態が「integrity」のある状態。恥の文化の場合には、バレなければいいという考えになりがちなんですけれども、「integrity」という言葉があれば、そういう概念がもっと育つだろうということです。強いて日本語に訳すなら「節」だろうけれど、もう一つぴったりこないと松岡さんは言っていましたね。
土井:先ほどの『かたりの椅子』の最後のシーンは、りんこが二つのドアの前で立ちすくむところで終わるんですね。私は自分のコラムにこう書いたんです。
りんこの前にある2つのドアの一方は、リハーサルのように「変節し安定した生活を選ぶ自分」へのドア、そしてもう一方は、「豚汁の列に並ぶ、つまり職を失いホームレスになることをも覚悟で、“私”を貫く自分」へのドアなのだろう。果たしてりんこは、どちらのドアに入っていくのか、そういう謎かけをしたまま、演劇『かたりの椅子』は終わるのである。それは、観客の一人ひとりに、「あなたは、どちらにドアへ進みますか。実際いま、あなたはどちらのドアを選んで生きていますか」という問いかけのようにも思える。
これは私が書いた文章なんですけれど、やっぱり永井さんはそういう問いかけをされようとしたんですか?

永井愛
『歌わせたい男たち』
而立書房
永井:いやあ、私自身がいつも迷うと言いますか、根津さんのように、または佐藤さんや土肥さんのように、こういう時に信念を持って対応出来るかと考えると、ほんとうにどうだろうと考えてしまう。黙って従うのはしゃくだけど、ここまで闘えるんだろうかと思います。だから私自身に問いかけてるんですね。私はどっちへ行くだろうと。「integrity」ということを考えていないと、楽な方へ流れると自分では思います。
それから、あともう一つ言ってみれば、こういったことが学校で起きて、先生の組合もあるはずなのに、みなさんほとんど個人で闘っていらっしゃる。なんでこんなに苦しい、つらいことを、個人でやらなきゃいけないんだろうかと思うんです。例えば、保護者だとか他の先生たちが「それはひどいよ」と言ったら、こんな苦しい闘いになりませんよね。血の滲むような闘いになる前に、他の人たちが「これは違うよ」と言わなければだめだろうと思うんです。
現にイギリスではそうだって言われましたね。イギリスもたくさんの問題を抱えている国ですけど、この『歌わせたい男たち』をイギリスで上演しようとした時に、まったく説得力を欠くと言われたんです。「イギリスなら、保護者が黙っていない。他の同僚が黙っていない。有り得ない。いつの時代の話ですか」と言われたんです。「現代です」と言ったら、「本当か?」って。その芸術監督は最初、私に何でも書いていいと言っていたんですよ。「人間に起きる出来事は人類普遍の問題だから、ロンドンに理解されようと頑張って書くのではなく、日本人のことを書いてもらえればそれは自然に普遍性を持つ」って。だから大丈夫かと思ったら、「すみません、普遍性ありません」って言われました(笑)。言論や思想の自由のない国ならともかく、少なくともロンドン基準ではありえないと。
土井:劇作家の方は自分から距離を置いて、自分とまったく違う設定を作って、自分は高いところから状況を俯瞰して観る──そういうふうにして作品を書いていかれるのかと私は思ったんだけど、やはり「自分はどうなんだろう」ということをいつも突き詰めながら書かれるんですね。
永井:そうですね。劇作家は「神の位置から」というより、鳥が空から見下ろすように全体を俯瞰する必要があるけれど、同時に蟻んこの目線も必要ですね。両方の位置を行き来できたらと思います。それに、「私は絶対に自分を貫きます。さて、あなたはどうですか」という言い方は、私には出来ません。「私もかなりだめかもしれないんですけど、あなたはどうなんでしょうね」というようなところですね。私にとって、それはすべて自分の問題です。このお三方のようなことができる人は少ないですよ。だから、人間がこんな厳しい目に遭うような状態を作らないようにしないといけないと思うんです。
土井:今おっしゃったように、この3人の方々は非常に強い方ですね。特に根津さんは、「日ノ丸・君が代」問題のシンボル的な存在の人で、「強い活動家」「揺るがない人」と見られている方です。ところが、意外だと驚かれるのは、あれほど「強い人」が自死を考えるところまで追い込まれたことがあるということです。自分の子どものことを考えて思い留まったといったことを映画の中でおっしゃるわけです。私は根津さんを撮影しながら、根津さんの脆さ、弱さという、人間にとって自然の姿、強そうに見えるけれど、やはりみんなどこかで本当は震えながら生きている姿に触れることができました。
佐藤さんは、いかにも弱々しく、今にも倒れそうに見えるけど、実際はそうではない。自分の支援者の会を「雪柳」と名付けておられるんです。柳って、雪が降ったりすると、その雪の重さでたわむんですって。ああ、折れそうだなと思うけれども、雪がすごく重くなると、ピーンと跳ね返すんですって。弱々しく見えても、芯の強い人だと撮影していてわかりました。
永井:佐藤さんは屋上から飛び降りたいとおっしゃっていて、根津さんも自死を考えたことがあると語っておられます。2人の先生が死を考えた。やっぱりそこまでいくんでしょうね。こんなことが起きているのに、それが「学校問題」として、学校の外に出てこない。だから意外に知られていないというのが、残念なことではありますね。
土井:永井さんがこの『かたりの椅子』を書かれた時も、おそらくそれを考えてらっしゃったと思うんです。私もこの映画を作る時に、「これが『日の丸・君が代』問題や教育現場の映画なんだと思われてしまったら、失敗作だな」と思ったんです。『かたりの椅子』で言えば、舞台はフェスティバルの話なんだけれど、りんこさんの生き方、入川の生き方というのは、「組織の中にいて、組織の論理と自分個人の倫理観、道徳観とがぶつかったとき、自分はどう生きるんだろうか」という問題だろうと思います。そういう体験をされた方はたくさんいらっしゃるでしょう。
だから私はそこの中に、例えば舞台は教育現場であり、「日の丸・君が代」の問題を一つのテーマに扱ってはいるけれども、私はこの映画を作るときに、私自身が生き方に迷い、この人たちの生き方を見ることによって、それを“鏡”にして自分をみつめ、「自分はどうなんだ。どう生きるんだ」ということを撮りながらずっと考えていたんですね。やはり永井さんは作品を書かれるときに、自分と離れて作るということはなかなか難しいでしょうし、その一方で作品に普遍性を持たすということと、どういうふうに調和をとっておられんでしょうか?
永井:舞台を観るというのは、一つの体験です。その場で起きることに、実際に立ち会うということです。ですから、リアリティというのは、観客を体験に呼び込む上で非常に大事なんですけれど、劇作家自身が知りつくしていることを書くわけではない。むしろ、リアリティーが持てずに、「現実にこんなことがあるのか?」と信じられないようなことを書きたくなる場合が多いでしょう。そこには、予測で近づくしかない。「こういうことじゃないだろうか」と。で、調べていくともっとすごいことが見つかったりして、やっぱり固定観念を覆される。そうやって、発見を探し求めていく。発見がないものは見せても面白くないし、リアリティーにもつながらない。『歌わせたい男たち』を書いた時にも、一人の不起立をめぐって、どんなことが起きるのか、校長は一体どういう立場なのかとか、書こうとする過程にたくさんの発見があって、私自身がまずそれを体験する。その体験が人に伝わるというふうになっていくんだと思うんですね。
(おわり)
【関連記事】
日々の雑感 182:演劇『かたりの椅子』とNHK番組改編事件の告発書(1)
日々の雑感 183:演劇『かたりの椅子』とNHK番組改編事件の告発書(2)
【関連サイト】
劇団「二兎社(にとしゃ)」 →書籍/DVD/パンフレット
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。