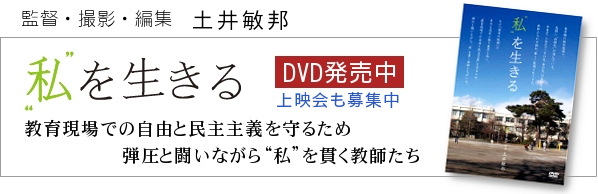映画『”私”を生きる』トークショー
ゲスト:高橋哲哉さん(前半)

2012年1月22日 東京:オーディトリウム渋谷
ゲスト:高橋哲哉さん(東大大学院教授)
土井敏邦(以下「土井」):今日は東大大学院教授の高橋哲哉さんに来ていただいています。実は高橋さんとは1998年、「戦争・心の傷の記憶」というNHK特集の番組でいっしょに仕事をさせていだたいきました。私が撮り続けてきた元日本軍慰安婦「絵を描くハルモニ」有名になった元「従軍慰安婦」の姜徳景さんを描いた3部構成の一部は私が姜徳景さんの映像と元にした番組で、高橋さんはそのとき「ナビゲーター」として登場されました。ですから、もう随分以前からのお知り合いです。
今日はその高橋さんにお話を伺います。20数分しかありませんが、まず高橋さん、ご覧いただいた率直な感想を聞かせていただけませんか。
高橋哲哉氏(以下「高橋」):皆さん、こんにちは。土井さんの作られた映画『“私”を生きる』を拝見しました。私の感想を申し上げれば、まずは3人の方──根津公子さん、佐藤美和子さん、土肥信雄さんを取上げておられるんですが、この三人の方が、敢えて言えば“日本の宝”だって思いましたね。「敢えて言えば」と言うのは、「日本の」を取ってしまってもいいということですが、敢えて“日本の”宝だと言いたい気持ちになりました。今のこの時代にこの日本のなかで、「“私”を生きる」ということがとても難しくなっている。なぜか。いろいろな理由があるんですけど、特に、21世紀に入ってからの日本の学校、なかでも東京、そして今、大阪が更に危うくなっていますけれど、そういう場所で「“私”を生きる」というのがどれだけ大変なことか。私は幸いこの3人の方と、面識がありましたし、他にもいろいろな方と交流する機会があって、お話をうかがったり、見聞きはしてきたんですけれども、その現場の難しさをある程度知っているだけに、こういう人たちがいてくれたっていうのは、現在はもちろんこれからも、「日本にとって宝物だ」ということをまず最初に思いました。
もちろん3人の方はそれぞれ微妙に違うところがあります。これは当然です。例えば「日の丸・君が代」の問題にしても、当然ながら、不起立をするということだけが唯一の振舞い方ではないわけですね。その人たちにとって、どういう闘い、どういう対応をするかについてはいろいろありうるわけです。土肥さんは立場上、ちょっと「君が代」では他の2人とは違う。根津さんや佐藤さんはそれぞれの想いから、ある意味では一番厳しい道を選択されたわけです。佐藤さんの場合でよくわかると思いますけど、「君が代」強制は本当に人を殺しかねない。そういう圧力がかかっている中で、よく生き延びてくださった。生き延びてくださっただけでも感謝です。同じ時代に同じ社会に、そういう宝物のような人がいてくださった。
それから次に、それを記録してくださった土井さんにも感謝です。この3人の方のような生き方は、なかなか人目に付きません。日本ではメジャーなメディアになればなるほど、こういうものは扱えないんですね。日本にとって、日本の社会にとって、ほんとうに大事な生き方をしている人がここにいるのに、個人としてメディアで活躍している人たちのなかには共感があったとしても、メジャーなメディアになればなるほどこういうものを扱えない。番組自体なかなか出来ないんですね。
土井さんはこれまでパレスチナ問題を含め、いろいろな問題に関わる貴重なドキュメンタリーを作ってきてくださったんですけれど、私自身がこの間、ある意味ではずっと思いを共にしてきたこの教育現場での自由の抑圧について、3人の人々に取材して、こういう記録を残してくださった。これも今後、宝物になると思います。日本の教育、そして民主主義、そういうものを考えたとき、土井さんの作ってくれたこの『“私”を生きる』という映画が、貴重なメディアになってくれるんじゃないか、そう私は思いました。
土井さんの作品の特徴は、やはり人を描いた、人間を描いたっていうことじゃないかと思います。『“私”を生きる』というその題名にも表れていますね。それぞれの人が“私”というのを大事にして、人生のその時々の場面でどういう選択をするか。右に行くか左に行くか──別に「右翼」「左翼」ということではありませんが──、そう考えたときに、「こっちに行ったら自分が、私が、“私”でなくなってしまうんじゃないか」と思う。そこで熟慮に熟慮を重ねて、決断をされたわけですね。そこに“私”が出てくる。もしそうでなければ、私が“私”でなくなってしまう。そこにそれぞれの人が表れていると思うんです。そこを土井さんは撮ってくださった。
映画には、3人の方のこれまで知らなかった面が出ていて、あまり難しい話ではなくておもしろかった面があります。根津さんはお父さんとそっくりですね。写真を見ると、本当に瓜二つという感じで。お父さんが経験された日中戦争のこと。根津さんの人生の大きな課題が、そこから始まったといっても過言ではないと思うんですけれど、それが印象的でした。それと対照的に、佐藤さんはフィジカルには(容姿の面では)、どちらかというとお母様に似ておられるのではないかと思ったんですけど、精神はやはりお父さん。お父さんの、やはり戦争をめぐる経験。これがやっぱり大きく佐藤美和子さんを作っていったということがよく分かった。ですから、精神的にはやはりお父さんにそっくり。土肥さんはご両親のことは分からなかったですけれども、なんといっても私はあの登校の場面でですね、「あと1分だぞー」とか「あと2分だぞー」とかいって、「笑ってる場合じゃないぞー」とか、あの辺が土肥先生の真骨頂だと思いますね。あそこに土井さんの人間性が全部出ていると思いました。あとは、私がグサッときたのはですね、「平等とかなんとか言っていても、東大にいるじゃないか、なんで辞めないんだ」。私がお会いしたときも、心の中ではそう思っておられたのかな(笑)。ちょっとあれ、グサッときましたね。そういうお人柄、人間が見えた、人を撮ってくださった映画、そういう意味でもこれは凄くいい映画に出来上がっているなと。ですから、皆さん、是非口コミでも広めていっていただきたい、そう思いました。
土井:ありがとうございます。そこまでそういうふうに言っていただけると光栄です。実は今日22日に高橋哲哉さんの新しい本が発売されます。タイトルは『犠牲のシステム─福島・沖縄』。もうご存知の方もいらっしゃると思いますけど、高橋さんは福島のご出身です。福島出身者としての思いがとてもこもった本なんですけれど、「犠牲のシステム」とはどういうことなんだろうと皆さん、疑問に思われると思いますので、そこだけちょっと読ませていただきます。ここがこの映画にも関わることだと思いますので、ちょっと読ませてください。
犠牲のシステムでは、或る者(たち)の利益が、他のもの(たち)の生活(生命、健康、日常、財産、尊厳、希望等々)を犠牲にして生み出され、維持される。犠牲にする者の利益は、犠牲にされるものの犠牲なしには生み出されないし、維持されない。この犠牲は、通常、隠されているか、共同体(国家、国民、社会、企業等々)にとっての「尊い犠牲」として理解され、正当化されている。

これが高橋さんのいう「犠牲のシステム」です。例えば、福島で言えば福島の原発です。あの原発事故で犠牲になったのは福島の方です。そしてその福島で生み出される電気を享受しているのが我われ首都圏に住む人間です。つまり我われは、福島の人びとを犠牲にしながら、電気を享受している。つまり私たちは「犠牲にする側」にいる。
高橋さんのおっしゃる「沖縄」もそうですよね。日米の条約で、我われは自分たちの「安全」というものを、沖縄の人に基地を全て押しつけることで、つまりあの人たちを「犠牲にされる側」に置きながら、我われ「やまとんちゅ」は本土で、「安全」を享受している。本当に安全を享受できているかは別問題ですが。つまり、我われは、沖縄の人たちに対して本土に住む我われは「犠牲を強いる側」ですよね。そういう切り口でこの本は書かれています。
私は実は福島の飯舘村という村のドキュメンタリーを作っています。片方で、沖縄の伊江島の阿波根昌鴻(あはごん・しょうこう)さんの闘い(1950年代、伊江島で米軍基地の拡張のために農民が土地を奪われようとするとき、阿波根昌鴻さんをリーダーとして農民たちが非暴力で闘った)のドキュメンタリーを作りたいと考えています。それはどういうことかというと、飯舘村も伊江島も「天災」ではなく理不尽な「人災」によって家や土地、故郷を追われた。その人びとの“痛み”は、イスラエル建国のために故郷を追われたパレスチナ人に通じるところがある。つまり、私は飯舘村と阿波根昌鴻の闘いを追うことで、「日本の中の“パレスチナ”」を描きたいと思いました。
ただ、私はこの高橋さんの本を読んだときに、私の中で「自分が犠牲にする側にいるんだ」という意識がすっぽり抜けていたことを教えられました。
もう一つ、私はこの私の映画の中に、これは過去のことですけれども、同じような問題を提示していることに気づきました。それは私たちが「犠牲にした側」、つまり「日の丸・君が代」、それに象徴されるかつての日本の天皇制、それに繋がるいわゆる軍国主義によって「犠牲にされた側」の視点を、我われがあまり気づいていないことです。気付かないからこそ「なぜ日の丸・君が代が悪いんですか」ということを我われは平気で言う。そのことに映画を作った私自身が、最初気づいていなかったんです。でも根津さんが、映画の中で「犠牲にされた側の視点にいれば、『日の丸・君が代』というのはこういうふうに見えるんですよ」ということを身体を張って教えてくださっていることに気がついたんです。そのあたりを、この本を書かれた高橋さんは、どういうふうに映画と結びつけていらっしゃいますか、福島の体験を通して。
高橋:そうですね。「犠牲のシステム」とか「犠牲の論理」について、この間ずっと考えてきました。もちろん「犠牲にする者」と「犠牲にされる者」と言っても、単純な関係ではない面があります。特に福島の場合は、いま土井さんが言ったのは、ある意味一番大きな側面ですが、私自身、福島の出身なんですけれども、大学入学以来、東京の人間になってしまって、40年くらいこっちで生きているわけです。だからこそ、かもしれませんけど、余計にその福島が犠牲になって自分が電力を享受するだけだったということにまったく気づかなかった。もちろん全国にある原発のどこででも事故が起きる可能性はあったわけで、今だってあるわけですけど、たまたま福島だったことで、私がそう感じるのかもしれませんが。
第一にはそういうことがありますが、他方で今回の事故では、首都圏の人間にも明らかに被害者の面がありますね。そして、経済的利益と引き換えに原発を受け容れてきた福島の人に責任がないともいえないわけです。原発の危険性をどれだけ考えてきたかっていうことを含めて。ですから、単純な話ではない。
福島と沖縄を並べて語ることにも私は躊躇があったんですが、その辺も、今回の本には多少書きこみました。でも、土井さんがおっしゃったように、戦前・戦中の日本の国家のあり方は、あからさまな「犠牲のシステム」だったと思います。軍国主義といわれますけど、その精神的支柱になった靖国神社も、私の考える「犠牲の論理」の典型になっているわけです。戦死した日本軍兵士たちが、国策に従って自分を犠牲にした、「尊い犠牲」だったとして顕彰されているわけです。その向こう側には、日本軍によって殺傷され、生活や財産やさまざまな権利を侵害された人たちが膨大にいるわけですよね。それがなかなか見えない。そして「日の丸・君が代」は、そういう歴史を全部背負っていて、佐藤さんもそれがあるからこそ苦しんでおられるわけなんですね。しかし土井さんのおっしゃるように、そこが見えていませんね、本当に。今の日本の社会の「光」の部分だけを見ていたのでは、これは本当に見えない。
沖縄も、多くの人には、いまだに見えていないのかもしれない。政権交代によって、普天間基地問題がぎくしゃくしましたが、それで初めて沖縄の基地問題が出てきたかのように思っている人すらいるわけですね。原発については、私自身、本当に福島の事故が起こるまで、こういう形で考えたことがなかった。地方の人たちに電力の供給源として原発を押し付けていながら、自分の故郷がどれほどのリスクにさらされているのか、それすら考えが及ばなかった。見えないものに、どうやって気づいていくのか。それを考えると、3人の方はそれぞれ教育委員会からは「不適格教員」のレッテルを貼られているようなものなんですが、ある意味では“最高の教育者”だと思いますね。それぞれの人の、“私”をかけた生き方が、生徒さんたちにとってとても大事なものを伝えていく。そういう意味で、最高の教育者だと思いました。
→ 次の記事へつづく
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。