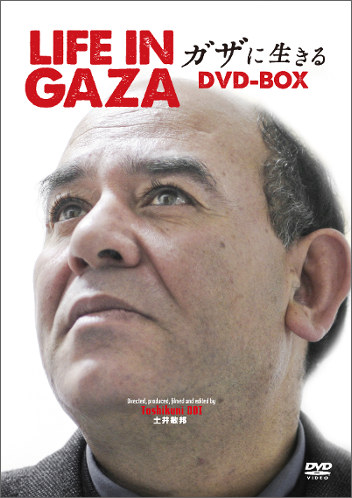日々の雑感 346:
なぜ映画『ガザに生きる』(5部作)を製作したのか
2016年1月21日
映画ができるまで

長い、長い年月だった。私が映像を撮り始めて間もない1993年10月から約20年間パレスチナ・ガザ地区で撮りためた膨大な映像を6時間強の『ガザに生きる』(5部作/BOX)として完成させるのに6年を要してしまった。
この作品制作のために支援してくださった多くの方々に、「映画を作ると言って支援金を集めておきながら、作品が出来上がらないとすると、ひょっとしたら、詐欺ではないか」と不審がられているのではないかという不安をずっと抱えてきた。
実は全体の原型はすでに3年前に大方、出来上がっていた。それを臼杵陽氏(日本女子大学教授)や錦田愛子氏(東京外国語大学准教授)らパレスチナ問題の研究者たち、永田浩三氏(元NHKプロデューサー・武蔵大学教授)ら映像のプロたち、また当時エジプト・アレキサンドリア駐在特派員で、中東報道の第一人者、朝日新聞記者の川上泰徳氏らさまざまな専門家たちに観てもらい修正に修正を重ねた。とりわけ川上氏からは第二部「二つインティファーダ」のインタビューが薄いことを指摘され、エルサレムで取材すべき人物を紹介していただいた。
しかし遅れの最大の要因は、2011年の東日本大震だった。
ジャーナリストとして看過できない大事件を目の前にして、何を、どう取材すべきか逡巡した結果、ドキュメンタリー映画3部作『飯舘村─故郷を追われる村人たちー』『飯舘村─放射能と帰村─』そして『被災地に来た若者たち』の取材・制作に3年を費やした。さらに震災関連以外にも、ビルマ(ミャンマー)の政治指導者アウンサンスーチー女史の来日を機に公開したドキュメンタリー映画『異国に生きる─日本の中のビルマ人─』(横井朋広氏との共同制作)、戦後70年目に公開した元「慰安婦」の証言ドキュメンタリー映画『“記憶”と生きる』などの制作が重なった。
もう1つ完成が遅れた原因は、英語版の制作に手間取ったことだった。
全5章、6時間を超える映画の英語字幕の制作は容易ではなかった。日本語を自由に使いこなす3人のネイティブ(英語を母国語とする外国人)の方々にお願いした。しかし一通り英訳が終わったと安堵したのもつかの間、また追加取材、編集の改変が必要となり、そのたびに翻訳の追加をお願いしなければならなかった。やっと英語訳ができても、さらに字幕として打ち込んでいく過程でも膨大な時間と労力を要した。
そこまでして、なぜ英語版の制作にこだわったのか。
パレスチナ・イスラエル問題に関する映画は、「遠い問題」として関心の薄い日本国内よりも、海外での需要がはるかに大きい。私は今回の映画のターゲットを日本国内だけではなく、欧米社会にも置いた。“パレスチナ”をめぐる国際世論にわずかでも影響をと願えば、まず欧米世界にアピールするしかない。そのためには英語版は不可欠なのである。
一方、「日本人が作ったパレスチナ映画」ということで、欧米社会で軽んじられる傾向は根強い。しかし同じアジアの日本人だからこそパレスチナ人に受け入れられ、心を開いてもらう現実もあるのだ。傲慢、自画自賛と笑われるかもしれないが、この映画の撮影にかけた年月、そして民衆の中に入っていく“深さ”において、欧米のジャーナリストたちに決して劣ってはいないはずという自負が私にはある。
制作が長引き、その間にも刻々とガザ地区の状況が変化していった。そのために追加取材をして新たな状況を付け加えなければならなくなった。しかしそこに大きな障害が立ちはだかった。イスラエル側からガザ地区に入るためにはイスラエル政府が発行するプレスカードが必要となる。しかし私はそのプレスカードの発行を拒否されたのである。
最初の発行拒否は2009年の夏のことだった。2008年12月〜2009年1月に起こったイスラエル軍によるガザ攻撃を取材し、NHKのETV特集や岩波ブックレットなどで報告した。さらにその年の5月から、元イスラエル兵たちの加害証言を描いたドキュメンタリー映画『沈黙を破る』を全国で劇場公開した。プレスカード発行を拒否されたのはその直後の2009年8月だった。その発行拒否は2014年夏のガザ攻撃の取材のため申請したとき再発行されるまで5回、5年間続いた。
刻々と変化するガザ情勢、しかしプレスカードのない私はイスラエル側からガザに入れず追加取材もままならなかった。このままでは『ガザに生きる』の完成はおぼつかない。残された道はエジプト側からのガザ入りだった。エジプト政府の許可申請など手続きに手惑いながらやっとガザ入りを果たしたのは、最後にガザを取材してから3年後の2011年12月だった。その時の取材映像を最後に『ガザに生きる』の仕上げにかかった。
しかし2014年夏、ガザにまた大事件が起こった。イスラエル軍による3度目のガザ攻撃である。しかも今回は51日間も攻撃は続き、死者2150人、負傷者は1万人を超え、破壊された家は約1万軒に及んだ。ほぼ編集を終えていた『ガザに生きる』に、その取材結果を追加しなければと考えた。しかしそうすれば、編集を大幅に変更しなければならず、完成までにさらに手間と時間がかかってしまい、完成時期がさらに大幅に遅れることなる。もうこれ以上の遅れは許されない。迷い悩んだ末、2014年のガザ取材は『ガザに生きる』シリーズから切り離し、ドキュメンタリー映画『ガザ攻撃 2014年夏』にまとめることにした。
なぜ『ガザに生きる』(5部作)DVDとしてまとめなければならなかったのか。
通常、1〜2ヵ月のパレスチナ取材で私が撮影する映像時間は平均して30〜50時間ほどになる。しかし番組報道できたとしても使用する映像は長くても1時間ほどだけだ。その残りの大半の映像は、人目に触れることなく倉庫に眠ってしまうことになる。その撮影のために長い時間と膨大なエネルギー、そして多額の資金を費やしたのに使用しなかった映像はすべて“無駄”になってしまうのだ。それではあまりにももったいないし、悔しい。
それだけではない。たとえテレビ局が欲しがるセンセーショナルな映像ではなくても、またテレビ局側がその価値を判断できなかった映像のなかには歴史的に重要な証言や映像が山ほど埋まっている。それを人の目に触れることもなく眠らせたままにするわけにはいかない。何よりも、貴重な時間を費やして、また中には身の危険を冒しても取材に応じてくれた多くの被取材者に対して申し訳が立たない。取材した私にはなんとしても世に出す責任がある。かといって劇場公開できる商業ベースの映画にもなりそうもない。残された方法は、自主ドキュメンタリー映画としてDVD化し公開することだった。
パレスチナ・ガザ情勢が日本のメディアが注目され報道されるのは、戦争や民衆蜂起(インティファーダ)、テロなどセンセーショナルな動きがあるときだけだ。しかしそういう現象を追っているだけでは、パレスチナ・イスラエル問題の本質は伝わらないし、地理的にも心理的にも遠い日本人の心には届かない。つまり「自分とは関係のない遠い中東の“問題”」で終わってしまう。私たち“パレスチナ”を報道するジャーナリストが伝えなければならないのは、日常生活を丹念に描きながら、そこで暮らす人びとを等身大かつ固有名詞で描くことで“同じ人間の顔”であり、そして封鎖や生活基盤の破壊、人間の尊厳の剥奪など“占領”という構造的な暴力を描き出すことだと考えている。
そのためにはやはり5部作6時間という尺が必要だった。
終着点がなかなか見えてこなかったこの映画制作をなぜ続けられたのか。それは強い個人的な動機があったからである。
なぜ30年近く、日本人に遠い“パレスチナ”と関わり、伝え続けるのか。それは現地の住民や周囲の日本人からずっと投げかけられ続けてきた問いだった。まさに私自身が自問し続けたテーマだった。つまり“私自身が生きること”と“パレスチナ”とはどういう関わりがあるのか、という根源的な問いである。その答えは、やはり私が撮りためた映像や、その時その時に書き残してきた文章をたどることで、自分がどういう人と出会い、何を聞き、何を考え、どういうことに心を揺さぶられてきたのか、その軌跡を地道にたどる作業を通してしか見出せない気がした。ドキュメンタリー映画の制作はその作業の一環だったと気付くのである。
この映画は多くの方々に支えられて完成した。私の取材を支援してくれたパレスチナ人権センターのスタッフたち、現地で私と共に現場を駆け回ったコーディネーターや通訳のパレスチナ人たち。彼らの支えがなければ、この映画は完成できなかった。
日本国内でも、内容の監修やアドバイス、編集作業などで研究者やジャーナリスト、翻訳のプロたちがサポートしてくれた。とりわけアラビア語の翻訳をチェックしてくれた山本薫氏、英語訳のチェックを引き受けてくれた中嶋寛氏、英語訳のデービッド・ウルヴォグ氏、ジャン・ユンカーマン氏、キンバリー・ヒューズ氏、英語字幕を手伝った横井朋広氏、そしてDVDや広報などのデザインを担当した野田雅也氏らにたいへんお世話になった。さらに多額の制作費のために支援してくださった多くの方々にも心からお礼を申し上げたい。さらに身近なところで連れ合いの土井幸美が物心両面で私を支えてくれた。
そして誰よりも、この映画全体の“道案内人”役を果たしてくれたラジ・スラーニに深く感謝したい。このシリーズの第一章をこのラジの半生とその思想を描くことに割いた。それはラジに対する私の心からの敬意と感謝と深い友情の表現であった。
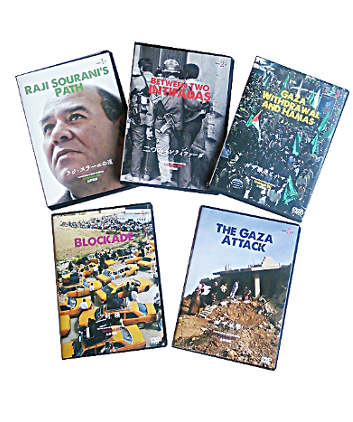
各章の狙いと込めた思い
第一章/ラジ・スラーニの道
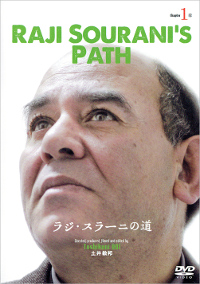
ガザで「パレスチナ人権センター」(PCHR)を立ち上げ人権活動家として活躍し、今やパレスチナを代表するオピニオン・リーダーの一人として世界に広くその名を知られるラジ・スラーニ弁護士との出会いがなければ、この『ガザに生きる』5部作は制作されることはなかったろう。この映画全体の“道案内人”がこのラジである。彼はまた、私がジャーナリストとして30年近く“パレスチナ”に伝え続ける上で、その視点、方向性を導いてくれた“パレスチナ問題の恩師”でもある。
この「一部」では、このラジの半生を通して、イスラエルによる“占領”とは何か、その中で、ガザの住民はどういう思いで、どう生きてきたのかを描く。私たちは「パレスチナ人」とマス(集団)で捉えがちだが、ラジという一人のパレスチナ人を固有名詞・等身大で描くことで、彼らもまた“私たちと同じ人間”であることを伝えるための一章でもある。
第二章/二つのインティファーダ
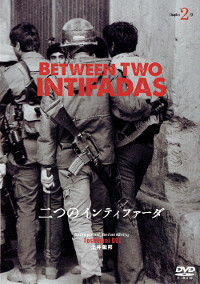
第一次インティファーダ、オスロ和平合意、そして第二次インティファーダと続く、パレスチナの歴史の大転換をもたらしたそれぞれの大事件の現場に私は立ち会ってきた。その大きな地殻変動の中での民衆の動きと思いを間近に感じ取ってきた私は、日本でのマスメディア報道や「専門家」の解説は現場の状況と大きく乖離していることが少なくないことを思い知った。“現場で取材した事実”を積み重ねることで、歴史の流れを読み解いていく──それがこの章の狙いである。
長い年月をかけて撮影した映像の中には、今や歴史の資料として重要な意味と価値を持ち始めたものも少なくない。例えば、民衆蜂起、和平合意、パレスチナ自治政府の誕生など歴史的な瞬間に対する民衆の反応、パレスチナ現代史に名を残し、すでに故人となった著名な政治指導者たちの証言である。
第三部/ガザ撤退とハマス
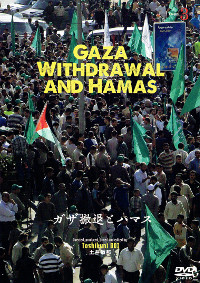
「ガザ撤退」という政治ショーを当時どう捉えたかは、パレスチナ問題の本質を見据えていたかどうかを計る“物差し”だったのだと、現在の混沌としたガザ情勢を観ると実感する。幸い私は、未来のガザ情勢を予言していたパレスチナ人やイスラエル人の鋭い分析を記録していた。
一方、「ハマス」というイスラム勢力の台頭とその過程、権力掌握、その後の堕落の流れを現場で目撃すると、政治勢力は絶えず流動し、固定した評価を下すことがいかに危険であるかを思い知る。それに翻弄される民衆の悲哀を目の当たりにすると、「善・パレスチナ VS 悪・イスラエル」という単純な二項対立で描けないパレスチナ問題の複雑さを改めて思い知る。
第四部/封鎖
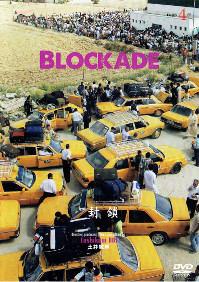
イスラエルの“占領”の象徴である“封鎖”の実態とその影響を映像化することは容易ではない。“地味”で映像で捉えにくく、“絵”になりにくいのだ。封鎖で生活必需品が不足し、物価が急騰していく。一方、農産物は輸出できず価格は暴落し、農民は生活が立ち行かなくなる。医薬品が不足し、治療のためにガザを出ることもできない。ガザ経済は停滞し、住民は失業と貧困に苦しむ。そして“真綿で首を絞める”ように、民衆はじわじわと、人間らしく尊厳をもって生きていく生活環境を奪われていく。それは爆撃、砲撃、銃撃のような目に見え、わかりやすい“直接的な暴力”ではなく、その現象が緩慢では見えにくい“構造的な暴力”である。「戦争」「蜂起」のように世界のメディアの注目を浴びることなく、国際社会の沈黙の中で“静かな死”が進行していく。
現在、パレスチナ報道に最も必要なことの一つは、この“占領”という“構造的な暴力”を描き出し伝えることだと私は考えている。緩慢で見えにくいその“暴力”を映像化し伝えるには長期にわたる“定点観測”しかない。この章はまさにその難事業への試行錯誤のチャレンジであった。
第五部/ガザ攻撃
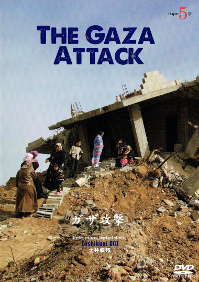
パレスチナ側に死者1330人、負傷者5300人の犠牲(大半は一般市民)を出した2008年12月〜2009年1月のガザ攻撃。私が現地に入ったのは「休戦」直後だった。取材を始めて気付いたのは、被害が人的な被害だけでなく、攻撃が生活基盤、産業基盤にまで及んだことだった。学校や病院まで破壊され、「休戦」の12時間前に、工業地帯が徹底的に破壊された。「ハマスの武装勢力を殲滅するため」というイスラエル側の主張とはかけ離れた現実を目の当たりにしたのだ。イスラエルはいったい何を狙ったのか。
参戦したイスラエル軍兵士たちの証言、一般市民の反応、有識者たちの分析から、このガザ攻撃の背景には、イスラエル人社会のイスラム世界への激しい嫌悪と恐怖、パレスチナ人に対する“非人間化”の意識、そしてガザを武器の実験場、軍事訓練の場とみなした軍部上層部の狙いが浮かび上がっていく。
さらに私は、目の前で父親を射殺され、自らも頭部に爆弾破片を抱えながらも生き残った8歳の少女の姿と声を通して、パレスチナ人の“人間化”をも目指した。
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。