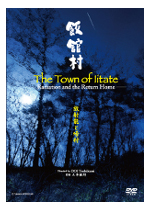日々の雑感 349:
大同生命地域研究賞・特別賞を受賞して
2016年7月31日(日)

突然、受賞を知らせる電話がかかってきたのは今年5月下旬だった。「大同生命地域研究賞・特別賞」と告げられても、それがどういう賞なのか、私はまったく知らなかった。
「なぜ私なんですか? 何に対する賞ですか?」と相手に聞き返したほど、私にはまったくその理由が思い当たらなかった。
その電話で、私の「長年、パレスチナ・ガザを定点観測し報道してきたこと」「『ガザに生きる』5部作の完成」などがその受賞理由であることを私は初めて知った。
長大な歳月とエネルギーを費やして取材した結果も、メディアではなかなか発表する機会に恵まれず、私の部屋の棚に眠ったままになっていた。その膨大な映像を、6年がかりでまとめた『ガザに生きる』5部作のDVD・BOXも、ほとんど注目されることもなく、大して注文も来ないまま半年が過ぎていた。「社会的に評価されなくても、自分の仕事の記録として残ればいい」と自身に言い聞かせていた矢先だった。
こんな地味な仕事をちゃんと見てくれて評価してくれる人がいるんだと驚き、それがうれしかった。
もう1つ、私が感動したことがある。この賞の第1回受賞者が、私がジャーナリストの道へ入るきっかけを作ってくれたルポルタージュ「戦場の村」の筆者である元朝日新聞記者・本多勝一氏であったことだ。本多氏の業績の足元にも及ばない私が、同じ賞をいただくことは恐れ多いことであるが、何よりも名誉なことである。
過去30回の受賞者の中には、他にも鶴見良行氏、高野悦子氏、野町和嘉氏、中村哲氏、村井吉敬氏など偉大な業績を残した著名人が並ぶ。そんな中に私のような無名のジャーナリストが名を連ねることはおこがましく、場違いなような気がする。でもたとえ間違った選考であっても、受賞による賞金は、取材費に事欠くフリーランスの私のとって何よりありがたい。
自分の受賞をHPで公開することは、気恥ずかしいが、今後、賞をいただく機会はもう二度とないだろうし、私の人生において1つの記念碑だから、「自己顕示」と失笑されることは承知の上で、私自身の記録として敢えてHPに記載する。
(選考理由の後に贈呈式でのスピーチを掲載しています)
土井 敏邦 氏〔研究特別賞〕
「ジャーナリストとして長年にわたりガザのパレスチナ人難民を映像記録として残した功績」に対して
大同生命地域研究賞 選考委員会
土井敏邦氏は1985年以来、パレスチナやイスラエルをはじめ、世界各地を精力的に取材してきた。その取材の成果は、『アメリカのパレスチナ人』すずさわ書店、1991年、『アメリカのユダヤ人』岩波新書、1991年、『「和平合意」とパレスチナ』朝日新聞社朝日選書、1995年、『パレスチナ ジェニンの人々は語る』岩波書店岩波ブックレット、2002年、『パレスチナの声 イスラエルの声』岩波書店、2004年、といった作品群に示されているように、パレスチナ人に関するルポルタージュを中心とした書籍の出版であった。
土井氏のルポルタージュの文体の特徴は、長時間にわたるインタビューに基づいて、映像をそのまま活字化したような、視覚的な強烈なイメージを喚起するものである。そのため、読者は土井氏の描く臨場感のともなう独特の世界に誘い込まれ、土井氏とともに現場をともに目撃しているかのように、追体験のできる読書体験をもつことになる。
土井氏は同時に、1993年よりビデオ・ジャーナリストしての活動も本格的に開始し、報道映像やドキュメンタリー作品をテレビ・映画・DVDで発表するようになった。そのドキュメンタリー作品の特徴は、ナレーションや音楽など余分な要素を排して、簡単なキャプションだけをつけ、関係当事者に直接語らしめるというドキュメンタリー制作上の手堅い手法を採用している。したがって、その映像からは現場に吹き渡る風と音、人びとのざわめき、自動車のエンジン音といった生活音もそのまま録音されることになり、取材現場の空気がそのまま伝わってくるという臨場感をともなっている。映像をとおして撮影対象そのものに語らしめるという手法をとることで逆に真に迫る絶大な効果を上げることに成功している。
土井氏のDVD映像ドキュメンタリーの代表作は『ファルージャ 2004年4月』2005年、『沈黙を破る』2009年、(キネマ旬報ベスト・テン【文化映画部門 第1位】/日本映画ペンクラブ賞【文化映画 ベスト1】/石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞)、『"私"を生きる』2010年(2010年度・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル奨励賞受賞)、『異国に生きる─日本の中のビルマ人』2012年(文化庁映画賞 文化記録映画優秀賞)、である。
土井氏は以上のようなドキュメンタリー作品によって数々の賞を受賞しており、文字通り日本を代表するドキュメンタリー記録映画監督であると高く評価できる。
さらに、土井氏のジャーナリストとしての功績で特に強調しなければならないのは、パレスチナのガザ地帯における長年の定点観測によって撮影したDVD作品である。ガザは1967年以来、イスラエルの占領下にあったが、2005年にイスラエル軍がガザから撤退し、以後、現在に至るまで封鎖状態にある。土井氏は、パレスチナ人難民一家の住宅に住み込み、その場所を定点観測地点として設定して、1980年代終盤以降、四半世紀以上にわたってガザに住むパレスチナ難民家族を中心に撮影し、その時々のパレスチナ人指導者を含めてパレスチナ人の日常生活とその破壊の実態を継続的に取材してきたのである。そして、長年蓄積してきた映像記録を編集し、その集大成として2015年に『ガザに生きる』5部作としてDVD化したのである。この作品は、パレスチナを代表する人権活動家の弁護士ラジ・スラーニの解説を通して、第1次インティファーダ(民衆蜂起)(1986年)からガザ攻撃(2008~2009年)までのガザの同時代史を映像でたどったものである。本作品は、第1章「ラジ・スラーニの道」、第2章「二つのインティファーダ」、第3章「ガザ撤退とハマス」、第4章「封鎖」、第5章「ガザ攻撃」の5部で構成されている。
同時に、『ガザに生きる』は日本語版とともに英語版も制作された。また、同作品はパレスチナ人政治指導者のインタビューも多数収録されており、パレスチナ現代政治史を考える上できわめて資料的価値が高いものであり、欧米諸国の大学等でも上映され、国際的にも非常に高く評価されている。
以上の理由から、土井敏邦氏は大同生命地域研究特別賞にふさわしい功績を挙げたジャーナリストとして顕彰するものである。
大同生命地域研究賞・贈呈式スピーチ
2016年7月22日

私がジャーナリズムの世界に足を踏み入れるきっかけになった1冊の本があります。
この賞の最初の受賞者である元朝日新聞記者・本多勝一氏の『戦場の村』です。
私が大学生の時でした。1960年代のベトナム戦争を描いたこのルポルタージュを読んだときの衝撃を今でも鮮明に覚えています。
『戦場の村』の前半では、「サイゴンの市民」「山地の人びと」「デルタ農民」などさまざまベトナムの民たちの生活をまるで文化人類学の論文の記述のように詳細に描きます。この記事が、朝日新聞に連載された当時、「政治を語らず、戦闘を描かずになんのベトナム・ルポか」という非難の声が上がったといいます。しかし、それら民衆の生活を描いたルポによって、読者は、「民衆の顔も、声も、体臭さえも、まるで実際、その体に触れた人のように想い起こし、暮らしぶりもすっかりわかってしまう」のです。
そしてその直後の第5部「戦場の村」で、その民衆に何が起こったかを乾いた文章で、詳細に描きます。例えばある病院の様子はこうです。
空爆の爆弾で生後1年4カ月の子が脇腹に穴があき、内臓が見えています。頭も割けている。顔に爆弾の無数の破片が突き刺さって血だらけになった20歳の母親が血染めの服からおっぱいを出して、無残な肉の塊となった我が子の口に含ませようとします。そして傷だらけの子の下半身に両手で抱きつきます。その涙は顔面の血と交わり、赤く染まっています。
その生々しい現場の様子が、映画のシーンを見るように、頭に浮かんできます。そして「ベトナム人」というマスではなく、名前を持った私と同じ等身大の1人の人間の“痛み”として、私の胸に迫ってくるのです。
それまで新聞・テレビ報道でわかっているつもりになっていた、「ベトナム戦争」の実態を、私は初めて自分の五感で感じ取ることができた瞬間でした。
「こんなルポを一生に一度でも書けたら、その後の人生はどうでもいい」
当時、私は心底思いました。
その取材現場として真っ先に思いついたのは、その直前の1年半の世界放浪の旅の途上で出会ったパレスチナの占領地でした。
大学卒業後、私はそのための準備にかかりました。
まず文章と写真の修行のために、2年間、中東専門雑誌の記者となりました。
次は取材資金作りです。英字新聞の求人広告でサウジアラビアでの日本企業の現地駐在員の仕事を見つけました。1年間、ひたすらお金を貯めるために働きました。
そして、1985年5月、第1次インティファーダが起こる1年半前に、私はジャーナリストとしてパレスチナへ向かいます。
それから1年半、占領地のヨルダン川西岸の難民キャンプ近くに下宿した民家を拠点に、占領地各地の町や村、難民キャンプを訪ね歩きました。
私は組織ジャーナリズムの中で訓練を受けたこともありません。取材は文字通り手探りでした。取材手法も暗中模索で、何度も行き詰りました。
そのたびに道しるべとなったのが、この『戦場の村』と同じ本多氏の著書『ルポルタージュの方法』でした。行き詰るたびに私はこの2冊の本を何度も何度も読み返しました。
帰国後、半年間、広島の留学生寮にこもって書き上げたのが、この「占領と民衆─パレスチナ」です。思い立ってから本を出版するまで7年の歳月を要しました。
「戦場の村」を本多さんが朝日新聞に連載する時のオリジナルタイトルは「戦争と民衆」でしたから、私の本のタイトルはそれを真似て「占領と民衆」としたわけです。
その後、私はパレスチナの現代史の節目節目に、現地を訪ね、取材を続けることになります。第一次インティファーダ、湾岸戦争、オスロ合意、第二次インティファーダ、イラク戦争、ハマスによるガザの実効支配。ガザの封鎖、ガザ攻撃……。
そして、いつの間にか30年近い歳月が流れました。
「なぜ日本人のあなたが、遠いパレスチナにそんなに長く関わり続けるのか」──パレスチナ人からも日本人からもそう問い続けられてきました。それは私自身の自問でありました。
正直言って、パレスチナは日本人にとって地理的にも心理的にも遠い。その現場を取材しても、なかなかテレビや雑誌などで取り上げてもらえません。結果をメディアで発表できなければ、私のようなフリーランスは取材費など経費は全部赤字です。
しかし、それでも私が30年近く、私がパレスチナへ通い続けたのは、金銭に代えがたいものをパレスチナから得ているからだと思います。
私はこれまでエリートコースとは真逆の挫折の繰り返しで、先の見えない不安定な半生でした。還暦を過ぎた今なお生き方が定まらない不安に震えています。
だからこそ、過酷の現実の中で、人間性を失わず、希望を見失わず生きるパレスチナ人は私にとって、自分の“生き方”“在り方”を根本から問いただされる存在でした。
私が住み込んだガザ地区最大の難民キャンプのある家族は、14人家族でしたが、仕事があるのは1人だけ。その1人が14人の家族を支えていたのです。
めったに肉を口することもできない。たくさんの兄弟たちは、狭い部屋に文字通り“川の字”になって寝ます。
貧しい家庭でしたが、それでも、家じゅう、兄弟や親子の間の会話や笑い声が絶えません。家族はお互いを思いやり、助け合い、強い絆で結ばれていました。
私の通訳をやってくれた家族の1人の大学生に、「奨学金を手に入れて欧米へ留学し、自分の道を切り開いたら?」と問うたことがあります。すると、その青年は「僕の幸せはこのコミュニティーの中にあり、僕の家族の中にある。自分独りが幸せにはなれない」と答えたのです。
パレスチナ人とりわけガザの住民たちは、イスラエルの占領、空爆や砲撃、封鎖による抑圧と貧困のなかでも、彼らはその“人間性”と“人としての尊厳”を失うことなく、現地にしっかと根をはって生き続けています。
その人たちの中で、私は他に代えがたい大切なことを単に言葉や理屈によってではなく、彼らの“生き様”そのものによって教えられるのです。
「祖国とは何か。社会とは何か。家族とは何か。そして抑圧や自由とは何か。人間の尊厳とは何か。そして生きるとはどういうことなのか」と。
私にとって“パレスチナ”とは、文字通り“人生の学校”でした。
今、「なぜお前は“パレスチナ”にこだわり続けるのか」と問われれば、私はこう答えます。
「あの現場が、私が生きる意味と力を与えてくれるから」と。
私がジャーナリストへの道を歩むきっかけを作ってくれた本多勝一氏が最初に受賞した同じ賞を、本多氏の業績にはほど遠い、まだ道半ばの私がいただくことにためらいもあります。
しかし同時にこれほど名誉なことはありません
この賞は、「本多氏がベトナムでやったように、『顔も、声も、体臭さえも、まるで実際、その体に触れた人のように想い起こす』ように、パレスチナ人を伝え続けろ」という激励なのだろうと思います。
あまり名も知られない私の、地味な仕事に光をあててくださり、私を推薦していただい先生方に心よりお礼を申し上げます。
今年63歳になります。その私が、これからどれだけあの厳しい現場に通い続けられるかわかりません。
ただ私の中に、「こんな理不尽なこと、不条理なことが、なんで許さるか!」という自分の中から沸き立ってくる“怒り”と、「伝えたい」という気力と情熱が続く限り、たとえ将来、車椅子に乗ってでも、現場へ向かうつもりです。
それが私にとって“生きること”だからです。
ありがとうございました。
→ 次の記事へ
【出版のお知らせ】

【書籍】「“記憶”と生きる」 元「慰安婦」姜徳景の生涯
(大月書店)
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。