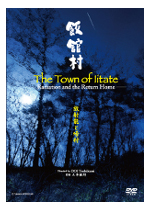日々の雑感 350:
「フクシマ」取材と『チェルノブイリの祈り』
2016年8月15日(月)
長くコラムを書くことから遠ざかってしまった。世界や国内の政治・社会の動き・出来事について、自分の胸に去来する思いを記しておこうと思ったりもしたが、それがどれだけの意味と価値があるのかと思うと、書く気力は萎えた。
それに何よりも、いま私はじっとパソコンに向かって自分の思いを書き記す心の余裕を失っている。
最近、机の置き時計のデジタル数字が正確にそして確実に1秒ごと増えていくことに、そら恐ろしさを感じるようになった。それが私の人生の残り時間、つまり“死”へのカウントダウンのように見えてしまうのだ。やっている仕事に、目に見える進展や成果もないまま、時間だけが過ぎていく。心の中で「お前は何をしているんだ! 急げ、急げ! 休んでいる間はないぞ。いまの仕事を早く片付けろ! 次のあの仕事が待っているぞ!」と自分に、もう一人の自分が叫んでいる。何をすれば、後ろから追い立てられるようなこの“焦り”、強迫観念から解放されるのか。やはり、「ゴールの見えない遠大な計画であっても、その実現に向かって、遅々とではあるが、自分は確かに動いているのだ」と自分を納得させるために一歩ずつでも動き続けるしかあるまい。
今、私がやり遂げなければと思う課題が2つある。1つは来年、50周年を迎えるイスラエルによるパレスチナ占領の現状を取材し、これまでの長い占領の取材映像をまとめる新たなパレスチナのドキュメンタリー映画を作り上げること。
そしてもう1つは、福島の証言ドキュメンタリー映画の完成だ。
2014年3月、東京池袋・豊島公会堂で開かれた「福島原発告訴団」による「被害者証言集会」で、原発被害者たちの証言を聞いたのがきっかけだった。800人を収容できる会場は満席だった。彼らの訴えを聞きながら、「この切実な声を、この会場の800人にしか聞いてもらえないのはあまりにもったいない。これら原発事故の被害者たちの切実な声を記録し残そう」と決意したのはその時だった。
それから告訴団団長の武藤類子さんらの紹介で、原告団のメンバーたち福島各地に訪ね歩き、インタビューを繰り返してきた。その数は数十人に達し、一旦、テーマごとに証言映像を粗編集してつないでみた。しかし、自分の胸にストンと落ちない。“胸に染み入る深さ”がないのだ。行き詰った。
2015年は、映画『“記憶”と生きる』の公開・上映活動と秋は1カ月半のパレスチナ取材でほとんど福島へ通えず、福島取材と映画制作は一時中断した。
そして今年春、「フクシマ」のドキュメンタリー映画の完成をめざし、取材を再開した。
「事故から5年経った今、被害者たちがどういう現状に置かれているのか。どういう思いであの事故を振り返っているのか。どういう“心の傷”を負っているのか。将来にどういう思いを抱いているのか」を証言としてきちんと記録し、残したいという思いが企画の原点だった。
しかし取材を再開して数カ月になる今なお、誰にインタビューするのがベストか、どうやってその人物をみつけるか。どうすれば本質的なことを聞き出せるのか、その具体的な手法や方向性がなかなかはっきりと見えてこない。かといって、福島から遠く離れた自宅でどんなに資料を読み考え込んでも少しも解決の道は開けない。現場で試行錯誤するしかない。そう痛感し、4月以降、1、2週間に一度ほどの割合で福島に通っている。かつて取材した知人たちに会って「フクシマ」の現状などの情報を収集し、インタビューすべき被害者たちを紹介してもらう。だが、そこでまた壁にぶち当たる。紹介しもらった被害者たちに電話しても拒絶されたり、メールやFAXで取材を申し込んでも返事もない場合もある。いったん取材に同意した人からも、その後、連絡が途絶えてしまうこともあった。「もう思い出したくねえ」「今さら、後ろを振り返っても仕方ねえべえ」「以前メディアの取材を受けたが、言ったことをちゃんと伝えてもらえなかった。もううんざりだ」という答えも返ってくる。
数日の福島滞在で1つのインタビューも取れないことも一度や二度ではない。やっとインタビューにこぎつけても、こちらが求めている「心に届く深い話」がなかなか聞き出せない。徒労と挫折の繰り返しでどんどん月日が経っていく。なかなかトンネルの先の灯りが見えてこず、方向性が定まらない。ほんとうに形になるのか、インタビューに答えてくれた人たちを裏切ることになりはすまいかという不安で、心が折れそうになる。

そんな時、1冊の本に出会った。昨年、ノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチ著『チェルノブイリの祈り』。事故から10年後に発表された事故被害者たちの証言集である。そこにはアレクシエービッチ自身の解説はない。ひたすら被害者たちの生々しい語りが続く。しかもそれは単なる「事実の羅列」ではない。その言葉が、読む私の心に深く染み入るのだ。これまでチェルノブイリに関しては多くの著書を読み、映像も見てきたはずなのに、チェルノブイリ事故の実態と、それが住民にもたらした影響が、これほどまでに生々しく胸に迫ってくる作品に出会ったことがなかった。「被害者の証言」だけの作品なのに、なぜこれほどまでに私は衝撃を受けたのか。
『チェルノブイリの祈り』の「訳者あとがき」に松本妙子氏がこう書いている。
「なぜもっと早くこの本を書かなかったのか」という読者の問にたいして、アレクシエービッチは、事故後まもなく取材のために汚染地に入ったことを明かしている。
「実は、10年前に書きたいと思ったのです。書こうともしました。何度も汚染地に足を運び、科学者や軍人に会い、自分の目で見、いろいろ話を聞きました。しかし、わたしは、事故をきちんととらえ、事故の意味を探るための理念も方法も持ち合わせていませんでした。いまわたしが本を書いても、事故の緊急リポートにすぎず、本質はすっぽり抜け落ちてしまうであろうことを、すぐに悟ったのです。のちにそのような本や映画が何百も書かれたりしましたが、わたしは自分の無力さを感じ、いったん身を引きました。
その後アレクシエービッチは長い年月をかけて「自分の頭でじっくりものを考える」人びとをさがしてはインタビューし、彼らが体験したこと、見たこと、考えたこと、感じたことを詳細に聞き出した、取材した相手は子どもからお年寄りまで、職業もさまざまで、300人にのぼるという。この人々のことばを借りて「いったいなにが起きたのか」を解き明かそうとしているのだが、それは「映画でも見たことがなく、本でも読んだことがない」ことであり、「だれからも聞いたことがない」ことであり、さらに「私たち人間の五感がまったく役に立たない」ことであった。
アレクシエービッチが試みたのは恐ろしい話を集めることではなく、事実のなかから新しい世界観、新しい視点を引き出すことだった。つまり、別の視点からチェルノブイリをとらえることである。アレクシエービッチはこうもいう。
「わたしはチェルノブイリの本を書かずにはいられませんでした。ベラルーシはほかの世界の中に浮かぶチェルノブイリの孤島です。チェルノブイリは第三次大戦なのです。しかし、わたしたちはそれが始まったことに気づきさえしませんでした。この戦争がどう展開し、人間や人間の本質になにが起き、国家が人間に対していかに恥知らずな振る舞いをするか、こんなことを知ったのはわたしたちが最初なのです。国家というものは自分の問題や政府を守ることだけに専念し、人間は歴史のなかに消えていくのです。革命や第二次世界大戦の中に一人ひとりの人間が消えてしまったように。だからこそ、個々の人間の記憶を残すことがたいせつなのです」
なぜこれほど読む者の心を揺さぶる語りを聞き出せたのか。どうすれば「事故の緊急リポートにすぎず、本質はすっぽり抜け落ちてしま」はないドキュメントが生み出せるのか。私の「フクシマ」取材の行き詰まりを抜け出すヒントがここにあるような気がする。
アレクシエービッチの言う「長い年月をかけて『自分の頭でじっくりものを考える』人びとをさがしてはインタビューし、彼らが体験したこと、見たこと、考えたこと、感じたことを詳細に聞き出」すという言葉にハッとした。しかし同時に、「『自分の頭でじっくりものを考える』人びとをさが」すことがそう容易ではないことを「フクシマ」の現場を取材した体験から身にしみて実感している。「語ってくれる人」を探すことさえ苦労する状況なのだ。しかも「『自分の頭でじっくりものを考える』人びと」を事前に見分ける眼力は私にはない。私にできることは、あらゆる伝手をたどって「語ってくれる人」を探し出し、とにかく手当たり次第、話を聞くこと。そのインタビューの中で、「『自分の頭でじっくりものを考える』人びと」かどうかを見極めることしかないのだ。
「恐ろしい話を集めることではなく、事実のなかから新しい世界観、新しい視点を引き出すこと」「別の視点からチェルノブイリをとらえること」も、凡人にはなかなか真似ができないことだ。それはアレクシエービッチという特異な才能をもつ書き手だから可能だったのかもしれない。
この著書(岩波現代文庫版)の「あとがき」にジャーナリストの広河隆一氏が、著書の中でも最も感動的な証言の1つ、冒頭の消防夫の妻リュドミーラの語りについてこう書いている。
リュドミーラの力だけではないことは、私にはわかる。なぜなら私自身も昔彼女に会って話を聞いたことがあるからだ。しかし私が書き留めた言葉は、アレクシエービッチのそれとはまったく違っていた。私の記録には、輝きの片鱗も見られない。事実の羅列にすぎない。アレクシエービッチだからなしえたことがあったのだ。
アレクシェビッチの仕事は、最も過酷な形で崩壊させられていく人間の姿を、生命の尊厳で書き留めていくことだったのだ。それは決して覆い隠すことで守られていく尊厳ではなく、言葉の極限まで語りつくしていきながら、守られていく尊厳だった。
アレクシェビッチのこの本は、ドキュメンタリー文学の最高の傑作ともいえる力で驚くべき世界を伝えている。言葉とはこうしたことを成し遂げるために存在しているのか、と思うばかりだ。
その力を私自身も渇望している。戦争で、核被害の現場で、撮影する写真に求められるものも、それに似た力を必要としているのだろう。砲弾で叩き潰された体、放射能で焼けただれていく体、腐臭、そうした記憶が、言葉や写真の形で、尊厳ある伝え方をされるためには、どれほど心のたたかいが必要なのだろうか。それともそれはその人に備わった資質と呼ばれるものだろうか。
どんな過酷な事象や体験をも、「尊厳ある伝え方」で伝えていく。単に目の前に現れる、また語られる現象や事実を、ただ表象をなぞるのではなく、その本質と尊厳を見出す目。私がいま「フクシマ」取材に行き詰っている原因はその欠落にあるのだろうか。それ以前に私は、「フクシマ」を伝えるためにこれまでに一体どれほどの「心のたたかい」をしてきただろうか。そもそも「その人に備わった資質」もないのに、「ないものねだり」をしているのだろうか。
しかし、ここでおずおずと引き下がりたくはない。「負けた。自分にはできない」と投げ出すのはあまりにも悔しい。それはまさに自分自身の尊厳と人生を放棄することに等しい。
「国家」が「自分の問題や政府を守ることだけに専念し、人間は歴史のなかに消えていく」その中で、こんな「備わった資質」もない私でも“伝え手”としてできることがあるはずだ。「国家」が暴走する今、「一人ひとりの人間が消えてしまったように」されていく世界の、そして国内の現状の中で、「個々の人間の記憶を残すこと」はこんな私でもいくらかはできるはずだ。アレクシエービッチにはなれなくても、『チェルノブイリの祈り』ほどの記録は残せなくても、それに近づきたい。それに人生を賭ける価値はある。
【関連サイト】
福島原発告訴団
岩波書店『チェルノブイリの祈り』紹介ページ
→ 次の記事へ
【出版のお知らせ】

【書籍】「“記憶”と生きる」 元「慰安婦」姜徳景の生涯
(大月書店)
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。