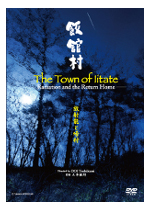日々の雑感 351:
『朝日新聞』への危機感
2016年8月24日(水)

(写真: 8月23日朝刊の『朝日新聞』と『東京新聞』の一面)
「勝った! 勝った! 金メダル!」。
テレビでアナウンサーが絶叫し、大新聞の一面に大見出しが躍る。高い視聴率を誇る「報道ステーション」もNHKの看板番組「ニュースウォッチ9」も連日 トップからオリンピックでの日本人の「健闘ぶり」を延々と伝える。しかも伝えるのはほとんどが日本人選手の活躍ぶりだ。私としては、銅メダルを取った日本人選手の競技より、もっとレベルの高い外国の金メダリストの競技を見たいのに、日本人が絡まないと見せてくれない。まるで日本人のためだけのオリンピックでもあるかのように。日本人が金メダリストを取ると、毎回、「日の丸」掲揚と「君が代」演奏を、涙ながらに歌う選手の顔のアップと共に映し出す。「国威発揚」にはこれほど絶好の素材はないだろう。かつてドイツのヒトラーがベルリン・オリンピックを「ドイツ・ナショナリズムの高揚」「国民の団結」を高めるために最大限利用した訳がよくわかる。4年後の東京オリンピックに何兆円かけても惜しまない為政者たちの狙いも透けて見えてくる。そう言えば、「ナチスに学べ」と公言した自民党幹部がいた。あの時は「憲法改正」のやり方への言及だったが、あの政治家だったら、近い将来、オリンピックも「ナチスに学べ」と本音を公言しかねない。
それにしても、日本のメディア全体がこの「国威発揚」に大政翼賛化し、そのオリンピック報道に世界や日本国内の動きに関するジャーナリズムの本来の仕事をほとんど放棄してしまったかのようさえ見える。
日本中がオリンピックに熱狂する最中の8月14日、NHK番組「こころの時代」(アンコール放映)でハッとする言葉に出会った。
二二六事件、日中戦争、そして太平洋戦争と、日本が急速に軍国化し、侵略戦争に突入していく歴史を身をもって体験した画家・堀文子氏の言葉である。
「乱世によって、私はものを観る目がちゃんとするようになりました。1つの世論に動かされない人間になりました。世論と闘うということは不可能に近いです、興奮状態になると。
その時に(国民が)好きなのはスポーツ、それからふしだらな男と女のスキャンダル。ちょっと似てるじゃないですか、いま。熱狂的でしょ、スポーツに。オリンピックなんていうと、莫大な金をかけても平気だと言いはじめちゃうでしょう。怖いですね」
(Eテレ「こころの時代 私の戦後70年「今、あの日々を思う」)
昨年秋に収録され、放映された堀氏の言葉は、まさにオリンピックに熱狂する今の日本社会を言い当てている。
オリンピックの熱狂を煽るメディアの象徴的な一例が『朝日新聞』である。
我が家は長年『朝日』を購読してきたが、数年前から『東京新聞』も同時に読むようになった。『朝日』だけでは国内の動きが把握できないと感じたからだ。
8月中旬の両紙の一面トップニュースを比べてみた(いずれも横浜版)。
- 8月12日(金)夕刊
- 『朝日』のトップは「金藤 200平 金/萩野 銀」
一方、『東京』は「伊方3号機再稼働/地震・避難…不安置き去り」 - 8月13日(土)夕刊
- 『朝日』 「原沢 銀/柔道 最多12メダル」
『東京』 「『戦争のない世界』理想回帰を/安世法1年を前に非戦朗読会」 - 8月16日(火)夕刊
- 『朝日』 「卓球男子 銀以上」
『東京』 「終わりの日が始まりの日/シールズ解散会見」 - 8月17日(朝刊)
- 『朝日』 「高橋・松友 バド女子 銀以上」
『東京』 「点字ブロックが便り/盲導犬の男性 転落/死亡事故」 - 8月17日(水)夕刊
- 『朝日』 「卓球女子 銅/実った愛の気配り」
『東京』 「高浜燃料取り出し開始へ/運転差し止め/長期停止見越し」 - 8月19日(金)(朝刊)
- 『朝日』 「逆転劇『軌跡』じゃない/伊調・登坂・土性 日本トリプル金 レスリング女子」
『東京』 「福祉用具レンタル原則自己負担方針/『体の一部』支え失う」 - 8月20日(土)(朝刊)
- 『朝日』 「樋口銀以上 男子レスリング」
『東京』 「駅2割 点字ブロックに柱/『危ない』電車の音にかき消されて」 - 8月23日(火)(朝刊)
- 『朝日』 「2020 東京で会おう/リオ5輪閉幕」
『東京』 「米軍増強 住民負担増の懸念/F35 岩国に16機配備へ」
(『朝日』は8月22日夕刊でもトップは「リオ五輪閉幕 東京へバトン」)
『朝日』はとりわけこの時期、オリンピックに、自社が主催する「全国野球選手権大会」、さらに「プロ野球」と、紙面の大半がスポーツ報道で埋まり、「スポーツ新聞」かと見紛うばかりだ。
ジャーナリズムとは何か。新聞の使命とは何か。2紙の一面記事を比べながら、私は改めて考えてしまう。「日本を代表する新聞」と自負する『朝日』は、何か大切なものを見失ってはいないか。
もう1つ、最近の『朝日』で気になるのが、やたらと増えた広告、とりわけ全面広告だ。発行部数の激減、経営悪化の中、記者たちの「高給」を維持するためか、多くの紙面を広告に割き、本来のニュース紙面がどんどん隅に追いやられていく。呆れた読者は『朝日』を離れていく。するとさらに部数は減り経営は悪化する。それを補おうとさらに広告を増やす、読者は一層、うんざりする……。悪循環である。
紙面だけではない。その“質”の劣化も著しい。とりわけ顕著なのが「天声人語」だ。元『朝日』記者にそういう感想をもらしたら、「『天声人語』の劣化は社内でも2、3年前から問題になっていました」という答えが返ってきた。私が気づくのが遅すぎたのだ。
かつて名文の手本として書き写しで文章修行した人も少なくなかったはずだ。私もその一人だが、ジャーナリストの道を入ってからも、限られた字数で時々の政治、社会、文化を鋭く切ってみせる“職人芸”に唸ったものだ。
しかし、最近の「天声人語」はまるで当たり障りのない「優等生の作文」を読まされているような文が少なくない。古典などさまざまな資料を引用にして「博学ぶり」を披歴し粉飾はされているが、「今、伝えなければならない重要なことが他にあるだろう!」「だから何なんだ! 一般論や誰もが思いつきそうな月並みな結論はもういい、あなた自身の主張は何なんだ!」と叫びたくなるのだ。8月22日朝刊の「天声人語」は、亡くなったむのたけじ氏の言葉を引用して「反骨はジャーナリズムの基本性質だ」と書くが、まさに最近のこのコラムに欠落しているのはこの“反骨”精神だ。いや、この“反骨”精神の劣化はコラムに限らず、今の『朝日新聞』全体に言えるような気がする。
もう1つ、今や『朝日』の看板となった「オピニオン&フォーラム」にも長年の『朝日』購読者としては違和感がある。たしかに国内外各界の第一人者、著名人へのインタビュー全面記事は読みごたえはあるし、資料としての価値もある。ただ、それを看板にするのはあまりに“安易”すぎないか。
私自身、ジャーナリストとしての仕事の大半がインタビューだし、私が最近深く感動した『チェルノブイリの祈り』に代表されるスベトラーナ・アレクシエービッチの代表作の大半はインタビューによる証言集だ。ジャーナリズムの重要な要素がインタビューであることは私も承知している。
しかし「日本を代表する新聞」が「インタビュー」を看板にすることに違和感を覚えるのだ。インタビュー相手の選択、質問の内容には『朝日』と担当するその記者の主張、視点が反映されているのは当然だが、そのインタビュー相手の主張を聞き、うまくまとめて新聞の看板にしてしまうことに、“安易さ”を覚えてしまうのである。
それを一層強く感じるのは、『東京新聞』の目玉、毎日2面を使って掲載される「こちら特報部」との比較をするときだ。一人または複数の記者が現場を走り回り、たくさんの関係者や専門家にインタビューして書き上げられる記事、文字通り“足で書いた記事”だ。しかもその記事には『東京新聞』の視点と主張がある。「これを伝えずにおくものか!」という気迫がある。いまの『朝日』が失っている“ジャーナリズムの原点”“反骨精神”がここにある。

かつての『朝日』には、そのような“目玉”があった。1ページの全面または大部分を使って1人の記者が書く短編ルポだ。本多勝一記者や疋田桂一郎記者など、『朝日』を代表する名物記者たちが腕を競った。それらの記事は大きな反響を呼び、世論を動かしたとさえ言われる。これらの記事も、快適な部屋で「第一人者」の意見を拝聴してうまくまとめた記事ではなく、記者が現場を駆けずり回る、いわゆる“足で書いた”記事だ。
本多勝一氏は著書「ルポルタージュの方法」の中でこう書いている。
「私としてこのような短編ルポルタージュをやるときが、苦労もあるけど、たいへんやりがいを感じるし、いわば『記者冥利につきる』ときです」
「短編ルポが圧倒的迫力を持つためには、第一に切り口の鮮やかさが必要です」「しかし、第二に、その切り口がいかにユニークでも、それを支えるだけの確固たる土台がなければ、読者を説得させるだけの力を持ち得ません。これは実は大変なことで、第一と第二の条件を満たすためには、短編ルポといえども膨大な取材が必要になってくるのです。たまたま取材の時間や量が少ない場合でも、それは当人がすでにその問題についてかなりの予備知識と問題意識を以前から持っていたためであることが多い。手ぬき工事ルポは、どうしても説得力に欠けます」
つまり世論を動かすようなインパクトのある短編ルポを書くために、文字通り血のにじむような取材が必要となる。「『専門家』や『有名人』へのインタビュー記事」にももちろん本質的な証言を引き出すために膨大な予備知識が必要であることは言うまでもない。しかし全面を埋める短編ルポに比べればはるかにその“労力”は少なくてすむ。私が最初に“安易”という言葉を使ったのはそういう意味も含んでいる。
しかも短編ルポの「切り口」「導き出した結論」に、取材し執筆した記者は全面的な責任を負わなければならない。しかしインタビュー記事なら、内容が非難にさらされるとき、記者は「それは私の意見ではなく、インタビューした相手の主張です」と逃げられる。そういう意味でも、インタビュー記事で全面を埋め、それを“新聞の看板”とすることに“安易さ”を私は感じてしまうのだ。
『朝日』に全面を埋める短編ルポを書ける記者がいないわけではあるまい。『朝日』の記者たちは、マスコミ入社試験の中でも最難関の1つであり何百倍という倍率を勝ち抜いてきた「優秀な」記者たちのはずだ。実際、中東や国内の現場で優秀な『朝日』記者にたくさん出会った。かつての長期連載記事「プロメテウスの罠」や現在連載中「新聞と9条」など、「さすが『朝日』」と思いなおさせる記事があり、それが書ける記者はいる。ただ大半の紙面は、優秀な記者たちの能力が『朝日』の紙面に十分反映されているようには見えないのだ。
それは紙面の方向性を決める幹部たちの責任なのだろう。最近、とりわけ2年前の「慰安婦問題」記事によって国内の右派勢力に激しい攻撃にさらされ、その対応の仕方に多くの国民の失望を招いてから、『朝日』は大きく購読者数や広告数を減らし、深刻な経営難に陥っていると聞く。経営者たち、幹部たちは経営を立て直そうと、「右派勢力の激しい非難に萎縮し、『朝日』の“色”を薄め、多数派に受け入れられる“無難な記事”で紙面を埋めようとしているように見える。
私は青少年時代に憧れた、アフリカの医療に貢献しノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュバイツァー博士の伝記に登場するあるエピソードを思い出す。
「荷物を満載した貨物船が大海で大嵐に出くわす。大波で木の葉のように揺れる船。沈没を恐れた船長は、部下の船員たちに船荷を軽くするため、できる限り荷物を海上に投棄するよう命じた。船員たちは必死に目の前の荷物を投げ捨てた。
翌朝、嵐は治まり、海は凪いだ。ホットした船長と船員たちは残った荷物を点検しはじめた。そこで彼らは生き残るために海に捨てた荷物の多くが、船員たちが生き残るために不可欠な食料や水だったことを知る──」。
『朝日』は同じような過ちをしようとしているのではないか。経営的に生き残るために、「多数派に受け入れられる“大衆路線”に舵を取れば、発行部数や広告数を維持できる」と考えてはいまいか。かつての『朝日』から今のような『朝日』になって、部数は増えているのだろうか。たしかにネット普及による影響・打撃は大きいだろう。若者たちは新聞を読まない、大学生さえ新聞を購読しなくなったとはよく耳にする。しかし『朝日』が部通を減らし、影響力を失いつつあるのはネットのせいだけではないような気がするのだ。
ジャーナリストであり、大学生時代に新聞を購読し始めて以来、数十年ずっと『朝日』の読者である私でさえ、そろそろ『朝日』を止めようと考えている。私だけでない。私の周囲の友人たちやジャーナリスト仲間の中にも早々と『朝日』から他紙に切り替えた者は少なくない。
その一方、「日本会議」に代表される右派勢力はあいも変わらず、自分たちと敵対する「リベラル派」の代表格、「護憲派」の牙城でもあるかのように『朝日』を狙い撃ちする。私は「いったい彼らにとって、牙を抜かれたような今の『朝日』のどこが怖いのか」と頭をかしげてしまう。
先の見えない仕事に焦り余裕を失っているはずの私が、これほどの時間と労力をかけて『朝日』の批判文を書いているのはなぜなのか。たぶん私の心の片隅に、まだ『朝日』に対する愛着、「がんばれ! 『朝日』がこけたら、日本社会がますます危なくなるぞ!」と激励する気持ちがあるからかもしれない。そうでなければ、何も言わず、ただ購読を止めてしまえばいいことなのだから。
【出版のお知らせ】

【書籍】「“記憶”と生きる」 元「慰安婦」姜徳景の生涯
(大月書店)
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。