日々の雑感 380:
パレスチナ報道の“金字塔”
川上泰徳著『シャティーラの記憶』
2019年6月20日
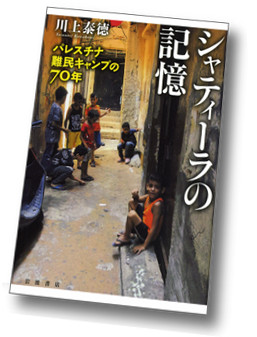
“人間”を描く
「なぜジャーナリストは危険地を取材するのか」――後藤健二さん殺害事件の直後に設立した「危険地報道を考えるジャーナリストの会」(略称・「危険地報道の会」)の中で、私たち世話人が議論し続け、日本社会に訴えてきた主題のテーマである。私自身、ストーンと自分の胸に落ちる答えがなかなか提示できず、モヤモヤしていた。
そんな時に、川上泰徳著『シャティーラの記録』を読み、「これだ!」と思った。
この著書に描かれているのは、レバノンの首都にあるパレスチナ人の難民キャンプ「シャティーラ」で暮らす住民たちの個人史と現状である。
1948年のイスラエル建国時に故郷パレスチナを追われた難民第一世代、同じ村出身の難民たちが「パレスチナ奪回」のために難民キャンプを作り上げた人々、1967年の第三次中東戦争でアラブ側が大敗北した直後から「パレスチナ人自らが解放闘争を」という熱気の中で闘いに人生を懸けた世代、レバノンの二つの難民キャンプ「タルザータル」「サブラ・シャティーラ」でのレバノン人右派勢力による虐殺で多くの家族を失いながら生き延びた住民たち、レバノン内戦やシーア派武装勢力による包囲・攻撃に耐え抜き難民キャンプを守り抜いた住民、そして差別・抑圧されるレバノンでの生活に絶望し自暴自棄になって麻薬に走る若者たち、希望を求めて命がけでヨーロッパをめざす住民たちとその挫折……。
その80人近い人びとの生々しい肉声が再現される。そこで語られるのは、それぞれの「人間の経験」(川上氏)である。つまり現地の人たちの個人史、家族、生活、心情が等身大・固有名詞で詳細に再現されるのだ。
さらに語り文に付けられた語り手たちの生き生きとしたポートレート写真が、私たち自身が現場でその声に耳を澄ましているような臨場感を生み出す。
ただ、この肉声の再現だけだったら、これほど深くその声は私たちには届かなかったかもしれない。その語りを補い、その言葉に生気を吹き込んでいるのは、その声が発せれる状況と背景をきちんと描き出す川上氏の「地の文」だ。その文は元新聞記者らしい、無駄のない簡潔で“乾いた”文章で、その状況が詳細かつ適格に表現される。
私たちジャーナリストが“パレスチナ”など紛争地の出来事を描こうとするとき、様々な証言などを積み重ねて、現在起こっている、また過去に起こった戦争や騒乱など事件・事象を再現しようとする。つまり取材し集める証言を、その事件・事象の描くための“素材”にしてしまいがちである。その証言で“人間”を描き出すのではなく、「事件・事象」を描き伝えることに主眼を置きがちになるのだ。
しかし『シャティーラの記憶』に登場する80人近い人びとの声は、事件を描く単なる“素材”ではない。それぞれの人生の断片、つまり川上氏の言う「人間の経験」そのものである。
川上氏は「あとがき」にこう書いている。
「紛争や戦争が続く中東であっても、女性や子供を含めて、普通の人々の話を聞くことで、現実が見えてくる」
「本書はシャティーラ難民キャンプという現場で生きる人々へのインタビューを重ねて、『パレスチナ問題』の向こうにある、人間としての経験を描こうとしたもので、私が(朝日新聞の)家庭面の取材で身につけたジャーナリズムの手法なのである。」
「故郷を追われる“楽園追放”の後、幾多の苦難を経て、束の間の成功や栄光はあったものの、転落とさらなる困難を味わい、いまは平和の中で閉塞状況にあえぐ。それは人間の歩みの縮図である。本書を手に取った読者が、パレスチナ人の経験の中に一瞬でも自分の姿を重ねることがあれば、私が本書に託した思いは伝わったことになる。」
故郷喪失、レバノン政府による過酷な差別政策、内戦、虐殺事件、難民キャンプの包囲・封鎖・攻撃など想像を絶する状況のなかで懸命に生きてきた人たちのその凄まじい生き様に、遠く離れた「平和」な社会で、「平穏」に暮らす私たちは、こんな過酷な状況の中で必死に生き抜く人々の姿に圧倒される。
川上氏は「人間の歩みの縮図」と表現するが、それは、紛争地などでの極限の状況下で人間の本性、“生”がむき出しになって露出するということではないか。その凝縮された“生”を突き付けられると、私たちは衝撃を受けると共に、私たち自身の“生”を顧みざるをえなくなる。つまり『シャティーラの記録』に登場するようなパレスチナ人たちの壮絶な半生の“鏡”に自らの生き様が映し出されるのだ。「では、自分はどう生きているのだろうか」と。
さらに彼らの姿が私たちは「“生きる”とはどういうことなのか」「死とは何か」「家族とは何か」「人間の幸せとは何か」「自分にとって“最も大切なもの”とは何か」と問いかけてくる。それが、川上氏が言う「パレスチナ人の経験の中に一瞬でも自分の姿を重ねる」ということなのだろう。
たいがいの人は「遠い地域の問題」に関心や興味は持たない。戦争など大事件には一瞬、注意を引かれることはあっても、すぐに記憶から消えていき、また目の前の日常の生活に埋没していく。そんな人間が最も関心を持つのは“人間”だ。“人間一人ひとりの生きる姿”だ。『シャティーラの記憶』はそれを描くことに成功している。
さらに言うならば、「なぜ、自分たちとは関係のない、遠い危険地で生きる人びと」のことを、ジャーナリストが自ら危険を冒してまで、伝える必要があるのかという問いへの一つの答えが、この『シャティーラの記憶』の中に提示されていると私は思った。
ジャーナリスト・川上泰徳の“特異性”
『シャティーラの記憶』のような記録を残すことは、他のジャーナリストたちが真似しようとしてもなかなかできないだろう。それは川上泰徳という特殊な経歴を持つジャーナリストだからできた仕事だからだ。
“中東専門記者”を育てなくなった今の新聞ジャーナリズムのなかで、川上氏は20年近く中東専門記者として現地を取材し、豊富な経験と知識を持つ特異なジャーナリストである。さらに川上氏の強みは、現地取材に不可欠な現地の言語、アラビア語に熟達していることだ。
アラビア語ができない私は、現地を取材するとき、通訳兼コーディネーターを雇い、その通訳を通して取材対象者の声を聞くことになる。その通訳の人件費は私のようなフリージャーナリストにとって大きな負担で、長期取材の最大の足かせとなっている。言葉ができれば、取材対象者を自分で探すのも可能だし、インタビューする相手の言葉も通訳に省略や要約されることもなく直に理解でき、即座にしかも適格に反応できる。同じ時間をかけても、その密度が通訳を介するよりはるかに濃いものになるのは当然だろう。
そんな川上氏が、4年間、毎年1ヵ月ベイルートのホテルに滞在し、シャティーラ難民キャンプに通い続け、200人近い住民(同じ人物に数回インタビューすることもあったいう)の証言を集めている。その取材の厚味が、そのまま著書の内容の厚味になっている。これほど深く広範囲なシャティーラ難民キャンプ住民の記録を残した例は、海外でもないだろう。英訳されれば、世界中でパレスチナ問題に関心を持つ人びとに読み継がれるに違いない。
ジャーナリスト・川上泰徳は、この『シャティーラの記憶』で、パレスチナ報道の、いや「危険地報道」の“金字塔”をうち建てた。

『シャティーラの記憶』(岩波書店)
2019年4月24日 第一刷発行
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。

