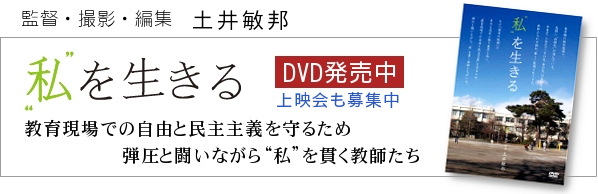土井敏邦・インタビュー
「“伝え手”として生きる」(3)
「“伝え手”として生きる」土井敏邦・インタビュー(1)
「“伝え手”として生きる」土井敏邦・インタビュー(2)
(2012年10月18日 公開)
ジャーナリストとして一番大事なことは「怒り」
【土井】 私はイスラエル政府からプレスカードの発行を拒否されたとき、抗議集会で「“パレスチナ”は私にとって人生の“学校”だった」と言いました。まさに私は“パレスチナ”に育てられました。私が最も尊敬するジャーナリストの1人にアミラ・ハスというイスラエル人の新聞記者がいます。オスロ合意以後、イスラエル人にとっては危険な占領地のガザやヨルダン川西岸に住み続け、アラビア語をマスターしてパレスチナ社会の中から占領の実態をイスラエル社会に伝えています。ジェニンの虐殺事件のときに、イスラエル人は復讐される危険があるのに、彼女はまっさきに現場に入りました。
彼女に「あなたのジャーナリスト活動の原動力は何ですか」と尋ねたとき、アミラは「私が車だとすれば、私のガソリンは『怒り』です」と答えました。
「こんなことが許されるか」という怒りを、私はパレスチナで学んだと思います。オリーブの木のことだけではなく、住民が理不尽に拘束され、土地が奪われる……「なぜこんな理不尽なことがまかり通るのか」という怒りです。ジャーナリストにとって一番大事なことの1つは、その“怒り”だと思います。
もうひとつ、私はあの人たちの人間性に感動し、成長をさせられたと思います。組織ジャーナリストは余裕がないかもしれませんが、ある現場に長期滞在し、そこで生きる人びとに惚れ込むと、自分という人間が育てられると思うのです。大治さんが“水俣”に関わって育てられたのと同じように、そこで出会った人に、ジャーナリストとしての感性や人間性を育てられるのです。そういう意味で、パレスチナは私にとって人生の“学校”だったと思います。
【大治】 非常によくわかります。理不尽への怒りと人間性への感動。いずれも、ジャーナリストの基本中の基本ですね。確かに私の場合も、40年前、水俣に通って一人また一人と多くの被害者に会っていくなかで、ジャーナリストとして鍛えられ立脚点をはっきりさせることができました。ジャーナリストは現場に出ないと、取材対象者の「まなざし」にさらされないと、鍛えられないものですね。
【土井】 私は、ジャーナリストは“黒子”であるべきだと思っています。伝える人間が表にしゃしゃり出て、「主人公」になってはいけない。それは恥ずかしいことです。自分の姿が見えないかたちで、感動したこと、伝えたい事実を、持つその手が見えないように、そっと視聴者や読者の前にさし出す。そして映像を見たり本を読んだりした人に感動を与え、後々「これは誰が書いたのだろう」「見えないけど、取材した人、撮った人が気になる」と思われたら、最高の栄誉です。
【大治】 土井さんの作品にはまさしくその気持ちが脈々とながれていますね。4部作のなかで注目を集めた『沈黙を破る』という映画は、イスラエルの反戦兵士たちの証言集ですよね。

【土井】 私は南京、韓国人被爆者や「従軍慰安婦」(元日本軍慰安婦)など日本の戦争加害の歴史を1つのテーマにしてきました。その一方で、長年ライフワークとして、パレスチナを追いかけてきました。しかしその2つのテーマが重なることはこれまでなかったのです。
しかし『沈黙を破る』の取材でイスラエル将兵たちの声を聞いたときに、私は中国での旧日本軍将兵たちの姿を想い浮かべました。本質的な類似に気付かされたのです。そのとき初めて、これまで無関係に思われた「日本の戦争加害」のテーマと、パレスチナが1つに重なりあったのです。そうい意味で、『沈黙を破る』という著作とドキュメンタリー映画は、私にとって記念すべき作品でした。
【大治】 イスラエル兵たちの活動を、簡単に取材をすることができたのですか。
【土井】 それはなかなか難しかったです。占領地にいると、兵士の暴行や非人間的な行為を目の当たりにします。20歳前後の青年がパレスチナ人の老人に人とも思わず平気で暴行を加える、そんな光景にものすごい怒りを覚えると同時に、「なぜこのようなことが平気でできるのか」を、いつか兵士にインタビューしたいとずっと思っていました。しかし占領地で兵士にインタビューすることは不可能です。無理だとあきらめていたとき、イスラエル人の友人が「『沈黙を破る』というグループの兵士たちが語り始めた」と教えてくれたのです。私はすぐにインタビューを申し込んだのですが、「これはイスラエルの恥だ。国内のメディアには話すが、できない」と断られました。しかし翌2005年に行ったとき、彼らが海外メディアにも話し始め、私もインタビューに成功しました。
私は、前年に拒否したのに今はなぜ応じたのか尋ねました。代表のユダは、「この問題はもうイスラエルだけの問題ではないことに気づいた」と答えました。つまり、これはイラクやかつてのベトナムでの米兵の問題であり、また日本もかつて中国で経験した、普遍的なテーマだと判断したというのです。もう一つの理由は、「国内でどんなに声を上げてもイスラエルは変わらない。外からの圧力がなければは変わらないことがわかった」とユダは答えました。
まだ20代半ばのイスラエル人青年たちの深い話を聞いているうちに、中国大陸での旧日本軍将兵の姿と重なってきました。「これは映画にできる普遍的なテーマ」だと気付いたのです。
【大治】 続編『ガザに生きる』5部作の制作が遅れているのは、イスラエルに入国する上で問題が起きたからですか。

【土井】 入国は問題ないのですが、プレスカードの発行を拒否されているからです。イスラエル政府はその理由を公表しませんが、「ガザ攻撃」(2008年暮から3週間)を大々的に報道した私をガザに入れたくなかったのだと思います。プレスカードを持たずに占領地でイスラエル兵に捕まると、取材テープや素材を没収される危険性があります。また出国時に空港で徹底的に調べられます。知人のあるテレビ局の記者は、プレスカードがなかったためにデモの映像が見つかり、数十万円もするカメラごと没収されてしまいました。イスラエルでの取材は、非常に危険がつきまといます。
現在はエジプトからならガザに入れる状況です。今、「ガザに生きる」5部作の追加取材を計画しています。17年間で撮りためた映像に、エジプト革命後、ガザのハマス政権はどう変わっていくのか、それを民衆がどう見ているのかなどを付け加えてドキュメンタリー映画として完成するつもりです。ガザを長年追いかけた人間としての責務です。そのためにも最新の情勢を取材して付け加えなければなりません。
素晴らしい生き方を伝えたい
【大治】 いまは飯舘村の原発問題と在日ビルマ人の問題も追っているのですね。
【土井】 軍事政権に迫害され、政治亡命した在日ビルマ人の生き様に感動し、断続的に10年ほど撮影した映像を元にドキュメンタリー映画を作っています。
震災が起こった3月11日、JVJA(日本ビジュアル・ジャーナリスト協会)の仲間たちは、その翌朝から一斉に福島へ向かって動き始めたのに、自分を突き動かす強い衝動が湧いてこなくて動けませんでした。自分にしかできないことはあるのか、私は何をしようとするのか、まったく見えてこなかったのです。
震災1週間後に向ったのは沖縄でした。基地建設のために農地を奪われた農民たちの姿に、私は“日本のなかのパレスチナ”を観た思いがして、以前から予定していた取材にかかったのです。しかしその間も「ジャーナリストなら、今の東北へ行くべきではないか」という思い、後ろめたさがずっとありました。そのとき、ふと「土地なのだ」と気付きました。一瞬に家と故郷を追われた人たちは、パレスチナ人と同じではないかと思ったのです。パレスチナと重ね合わせれば自分の独自の視点で追えるのではないか、そう考えたときやっと東北を取材する動機が持てました。そこがジャーナリストとして不器用なところです。
【大治】 土井さんは、自分の生き方と重ねながら取材をしていますね。
【土井】 フリーランスは、組織ジャーナリストと比べて経済的な基盤など条件がはるかに悪いので、取材する対象と自分の生き方がすり寄せられないと、自分が支えられなくなります。そうすることで自分が生きていくための“精神的な糧”、“生きている意味”を見出だそうとするのだと思います。フリーランスとして活動を続けるためには、自分の鏡として取材対象を重ね合わせられないと、私は自分を支えられないのです。自分が生きることと絡み合わせることができる対象に出会ったから、どんなに厳しい条件でも続けられると思います。
【大治】 それは、土井さんの作品が物語っています。『私を生きる』という作品は、人間として尊厳をかけて生きる選択をしている人たちに共感しながらインタビューしているのが見る者には伝わってきます。
【土井】 自分が感動しないもので、他人を感動させることはできません。感動した事柄をかたちを壊さないように伝えることが、私の役割だろうと思います。素晴しい人に出会ったら、「こんなに素晴らしい生き方があるのだ」と、映像や文章で伝えたいのです。
【大治】 それが土井さんの原点ですね。今日はありがとうございました。
→ 次の記事へ
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。