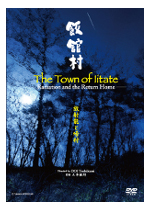日々の雑感 353:
映画『22』が日本人に突き付けるもの
2016年9月26日(月)韓国・高陽市にて

(写真:映画『22』より)
さまざまな作品に触れて、ドキュメンタリー映画には少なくとも2つの重要な要素が求められる、と私は最近考えるようになった。
まず1つは、「どうしても伝えずにおくものか!」という制作者の強い想いとメッセージである。「伝えたいもの」が見えない作品は退屈だし、つまらない。時には、「なぜ貴重な時間を割いてこんな映画を見せられるのか。時間を返せ!」と叫びたくなるほど腹が立つ。そういう時、私はすぐに劇場を出てしまう。山形国際ドキュメンタリー映画祭で何度もそういう体験をさせられた。
もう1つ重要な要素は、その伝えたいメッセージを声高に叫ぶのではなく、丹念な事実の積み重ねで伝えていくこと。しかもそれを押し付けがましくなく、感情を煽る音楽やナレーションでゴテゴテと粉飾するのではなく、すっと自然に観る人を“現場”に導き、その人の心にそっと作り手の想いを届ける、その手法・技術が求められる。押しつけがましくない、心に染み入るような美しい映像と自然音はその重要な要素だろう。
この2つの要素を備えたドキュメンタリー映画に出会える機会はそう多くはない。
2016年韓国の「DMZ Docs 映画祭」で、私はそんな稀有な映画に出会った。
中国に生存していた22人の元「慰安婦」たちを記録した郭柯(グォ・ケ)監督の『22』である。
まず感嘆するのは、その映像の美しさである。すでに80歳を超えた元「慰安婦」の老婆たちが、戦後、生まれた実子に守られて日々を送る姿、子どもを生めずに育てた養女に世話されながら生きる姿、家族もなく独り隣人やボランティアの世話で生活をつなぐ姿……、深いしわが刻まれたその顔の表情はいずれも暗く、寡黙だ。それを、名画を観るような見事な構図と色彩、ゆったりとしたカメラワークで映し出す。寒村の静かなロングの風景や住居のたたずまいを映し出す映像からは、極度の“貧困”の度合いを私たちは即座に読み取る。さらに深い陰影の中に映し出される老婆たちの表情から、彼女たちの「慰安婦」体験とその後70年を超える人生の想像を絶する過酷さを、観る私たちは否が応でも想い描いてしまう。言葉ではなく、映像が“語る”のだ。その映像の力を、老婆自身の、家族の、支援者たちの訥々とした証言の言葉がさらに補完していく。

この映画から私たち日本人は、かつての自国の軍隊、軍人たちが、1人ひとりの中国人女性の人生にどれほど癒すことのできない深い傷を残したかを、今さらのように思い知される。それは、私たち日本人が「慰安婦問題」という言葉から想像し、知っているつもりになっている生易しい現実ではない。
そして、この現実をほとんど知らず、いくらか知っても「もう過去のこと」として看過し、ほとんど罪悪感も持つこともなく、むしろ「戦争の被害者」面(づら)ばかりする私たちの在り方そのものを、この映画は問うている。しかし、これは声高な「日本の戦争責任」を追及する映画ではない。ただ犠牲者の老婆たちの日常の姿を淡々と、静かに私たちの前に突き出すのだ。問われているのは、私たち日本人がこの現実を、それを描いたこの映画をどう受け止めるかだ。私たち日本人は、まずこの映画を観なければならない。
→ 次の記事へ
【出版のお知らせ】

【書籍】「“記憶”と生きる」 元「慰安婦」姜徳景の生涯
(大月書店)
ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。